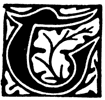 HE REVISIT OF THE GHOST. HE REVISIT OF THE GHOST.クリッサの不吉な予言は的中した。 「来たぞ」 ダグラスが低い声で呟いた。時刻は真夜中だった。 ごとんと足音。 ふっとランプが消える。あたりは真っ暗になった。 今夜は月が雲に隠れていたのだ。 暗い部屋の隅を、デューラムは息を呑んで見つめた。何か確実な違和感がそこにあった。肩が、と彼は思った。そうして足が。 しかしどれだけ目をこらしてみても、その隅は真っ暗闇で、ごくかすかに浮かぶ曲線以上のものを認めることはできないのだった。 今度こそテーブルのまわりで寝ずの番をしていた4人は、現れた気配を無言で見つめていた。場に満ちていたのはやはり恐怖と緊張ではあったけれども、昨日のそれとはずいぶん異なっていた。今夜女がやってくるのを彼らは予想していた——ある意味、待ちかまえていたのだ。 女がふたたび低い声で何かを呟き……そして、どうやら腕をあげ、彼らのほうを指さしたようだった。 影は動く。部屋の隅から彼らのほうに向かって—— ………… うめくような囁きがあった。闇の中で影が動揺したように大きく蠢く。 影はその場を動かなかった。否、動けなかったのだ。押しつぶされたような、かすかにしゃがれた呻きをあげて幽霊は身もだえた。 女がつなぎ止められているのは、クリッサが妖しいインクで魔法陣を描いた、まさにその隅だった。デューラムはクリッサの魔法陣が実際に効果を発揮していることに心底驚きながらも、円形の魔法陣のちょうど中心に立つ女を凝視した。 ひときわ大きな声が影から絞り出された。硝子の瓶の中に幾度も反響したような、低いものと高いものが幾重にも入り交じった声である。 「なんと言ってる」 「出せ、とさ。それを返せと」 デューラムのつぶやきに、ツァランが押し殺した声で答える。 「これか」 デューラムはテーブルの上から枯れた花を取り上げた。幽霊に向かって掲げてみせる。 「これがほしくておれを毎晩脅かしてたのか。悪いけど、もうすっかり枯れてしまったよ」 言葉は通じないはずだった。だがそのとき、ふたたび身もだえをするように、確かに影がうねった。怒りと悲哀が混じったような獣じみた唸りが響く。デューラムは一瞬、その声に気圧され唾を飲み込んだ。 だが、幽霊はクリッサの描いた魔法陣から出ては来られない。そうして、彼女が残した魔法の武器がある。デューラムは再度ごくりと喉を鳴らすと不敵に笑った。 「それでもこれがほしいのか。ほしけりゃそこから出てこいよ」 言った瞬間、デューラムの背中にぞっと鳥肌が立った。 「デューラム!」 イザクが鋭い警告の声をあげたのと、それは同時だった。闇の中の影がそのとき突如ふくれあがったのだ。びしゃりと嫌な音がするのと同時に、何か細長いものがそこからぬっと自分に向かって突き出てくるのをデューラムは感じた。魔法陣が破られた、と悟るより早く、彼はとっさに一歩後ろにひいていた。頬に何かが触れた。濡れて冷たく、ぬらりとした細いもの—— 指だ。 デューラムは思わず叫び声を上げた。手にしていた杖で手の主がいるとおぼしき場所を殴りつける。無我夢中だったが、空気のようでいてざわりとやわらかい、奇妙な手ごたえがあった。 「叩きのめせ!」 ダグラスが怒鳴る。「三回だ、デューラム!」 デューラムはがむしゃらに杖をその場所に向かって振り下ろす。二回、……三回! とたん、ぎゃっと動物めいた悲鳴があって、わだかまりがざあっと彼の目の前から後退する気配があった。 影は四人から離れた床の上、部屋の隅でうずくまった。デューラムは肩で息をしながらその様子を眺める。その荒い息の音に混じって、なにか声が流れた。か細く長い、女のそれとはっきりわかる声で、しゃくりあげるような響きがそこに絡んでいる。 ――泣いている。 幽霊は闇にうずくまる大きな黒猫のようにわだかまり、ときおりかすかに脈打ち、揺れ動き、震えながら、嗚咽した。その声のあいまに、ぽたぽたと水滴が木の床に落ちる音が響いた。四人はかたずを飲んでその様子を見つめた。昨晩の怨恨の塊のような印象から一転して、沈痛な声をあげながら、ただ惨めにむせび泣く女の姿がそこにあった。 デューラムは当惑し、自分の手の中にある杖を握りしめたりその手を緩めたりした。正直なところ、こうした状態は予想していなかったのだ。クリッサの悪霊対策は、まったく効かずにひどいことになるのか(どうなるのか彼は予想したくもなかった)、もしくは完全に撃退しえて幽霊がたちどころに消え失せるか、どちらかなのだと思っていた。 生きてる女だって泣きじゃくられたらどうしようもないのに——、そうデューラムはいらいらと考えた。泣き出したのは幽霊ときた! いったいどうしろと言うんだ。まるでこれじゃあ……。 ちらりとまわりを見ると、残りの三人も何ができるでもなく、泣く女をただ呆けたように眺めているばかりである。 幽霊はそのむせび泣きの合間に、低く何かを囁きはじめていた。独り言のような囁きだったけれども、何か、この場にいないものに訴えかけるような声音にも聞こえた。ツァランが居心地が悪そうに身じろぎするのを、少しずつ闇に慣れてきた目でデューラムは見た。 「何を言ってるんだ」 「恋人のことだな」短い答え。 「で、何と言ってるんだ」と、ダグラス。 ツァランは息をついた。しぶしぶといった様子で通訳をはじめる。 「……一人にしないでくれ、お願いだから一人にしないでくれ…… なぜ、わたしを置いていったのか。……なぜ、なぜ、わたしを一人にしたのか。……あの夜、確かに約束したではないか。あの池のほとりで約束したではないか」 床の上にうずくまった幽霊は、すうとまた腕を伸ばすようにその影を床に這わせた。デューラムはびくりと身動きしたが、幽霊が掴んだのは彼ではなかった。それはいつのまにか彼が床に取り落としていた、くだんの花だった。 そのときちょうど、月が雲から顔を出した。窓から一筋だけ月光が差し込む。 その細い細い光の直線のなかに、命なき手がゆっくりと浮かび上がり、花を持ち上げるのを彼は見た。そうして、ひからびた花びらのなれのはてが、はらはらと床に散り落ちるのを彼は見た。 「……王のための命など、あなたは持ってはいなかった。そのために捨てるべき命など、あなたもわたしも持ってはいなかった。 なぜ、なぜ、わたしを置いていったのか。なぜ、なぜ、わたしを一人にしたのか。……あなたがすすんで死ぬはずはない。あなたがわたしを残して命を抛(なげう)つはずはない。帰ってくると約束したのだから。わたしに誓ったのだから……」 「あの夜、あの月のない風のない、蒼ざめた夜に」 「わたしのもとに帰ってくると」 「そう誓ったのだから」 咽びいる声がゆらりと揺れる。 花が床に落ちた。かさりと乾いた音がした。 影は消えていた。 デューラムは以前に見た夢を思い出す。 痩せこけた子どもたち。男の影のない貧しい家々。村の広場の中央にそびえ立つ無機質な石碑。泣き叫びながらそれにすがりつく質素な身なりの若い女。 頭に浮かぶのはひとつの情景だ。 青い夜。大きな木の木蔭。 大丈夫だからと、その若い農夫は言う。恋人にひとつ口づけて彼は去る。 戦場へと。 残された女はその後ろ姿を唇を噛みしめて見送るばかりだ。彼女は恋人を引き留めたい。 ——行かないで。行かないで。置いていかないで。 だが彼女になすすべはない。 ——死なないで。 幽霊が呟いていたという台詞。 ——あの時の別れが最後だと思ったのに。 そして脳裏に浮かぶ、もうひとつの情景。 それは戦の嵐がひとしきり猛威をふるい、去った後の、荒廃した森の中だ。一人の女が木々の間をさまよい歩く。衣服はみすぼらしく汚れ、顔はやつれ髪は乱れ、まるで鬼女のようなありさまだ。女は何かを探しているようにあたりを見回しながら、腐りかけたいくつもの死体の間を縫うように歩き回る。 あるいは、木々の間に倒れ伏した一人の女。 女の顔は、森の中に花開くように広がった金色の髪でなかば覆い隠されている。 横に向けられたその顔のすぐ隣には、骨に肉と衣服のこびりついた、一体の骸。 見開かれた女の目は、彼女にかつて口づけをしたその男の、いまや見る影もなく肉の腐り落ちた顔に向けられている。 もう燦めくこともまたたくこともない硬直した女の瞳は、だがしかしその内奥に、生きていたときの懐かしい顔のまま安らかに眠る恋人の顔を映し出していただろう。 そうして女の唇は、うっすらと笑ってもいただろう。 爪のはがれたその指は、恋人の頬にいとおしそうに添えられていただろう。 ——二度と離れることはないはずだったのに、 兵肉食いの花。 中・大動物の遺骸を養分としてよく育つ花…… マーヤの無邪気な笑顔。「綺麗なお花でしょう。森の中に二輪並んで咲いていたの……」 ——あなたはまた死んでしまった。 枯れおちた花。 ぼっと橙の灯がともる。 デューラムはわれに返り、それから眩しげに目をしばたたかせた。 「大丈夫か、デューラム」と、ダグラス。 「ああ」 デューラムは短く答えると、目をぎゅっと瞑り、それから手で顔をぬぐった。 ダグラスとツァランの家の、いつも通りの居間だった。テーブルの上には四人分の水が入ったカップと、彼らが退屈しのぎにだらだらと興じていた盤遊び(ボード・ゲーム)の駒が散らばっている。 ランプをつけたのはツァランだった。彼はふうと大きく息をつくと、ずり下がるような格好で椅子に体を預けた。 「行ったな」 「ああ」 デューラムはやはり短く答えて、幽霊がうずくまっていたあたりの床を見た。そこにはいくつかのひからびた花弁と、乾いた茎が落ちていた。 ダグラスが魔法陣の描かれていたあたりに歩み寄り、ふむと鼻を鳴らした。魔法陣の一角は、なにかどす黒い液体で汚されていた。ダグラスはそのままテーブルに戻ってくると、どっかりと椅子に腰を下ろし、言った。 「……何年も泣き続けると目も溶けちまうもんかな」 沈黙が落ちる。 「はん」とツァランが声を出して鼻で笑った。「まさか。目が涙で溶けるのならおまえの肌がとっくに汗でどろどろに溶けていなくてはおかしいぜ。……おい、しっかりしろよ、おまえら」 「何がだ」 デューラムはとねりこの杖を、テーブルの上の散らかった遊び駒の横に横たえて、 「おまえだって、なんだか情のこもった訳をしてたぞ」 ツァランはじろりと彼の顔を見あげた。 「あれは直訳だ。脚色はしていない。だいたいぼくは情のこもった訳ができるほどあの言語を知らない」 彼はそこで唇を舐め、語気を強めた。「……喉元過ぎればその熱さを忘れるのも結構だが、単純にすぎないか? 言っておくがな、きみが殺されそうになったのはたった昨晩のことだぞ。クリッサが情にほだされるなと言ったのを忘れたのか」 「忘れちゃいないさ」デューラムはその向かいの椅子に腰を下ろすと、腕を組んだ。「でもな、ツァラン」 呼ばれた男はきつい視線でデューラムを見返した。デューラムは少し躊躇したが、言った。 「……おまえ、五百年から六百年前て言っただろ。そんなに泣きつづけたら溶けることもあるんじゃないかな」 ツァランは舌打ちすると天井を仰いだ。苛立ちのうかがえるため息を、再度大きく吐く。 彼はそれから小さく呟いた。 「……そうかもしれないな」 |