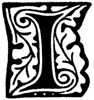 NTO THE HEART OF THE STORY. NTO THE HEART OF THE STORY.
「ふうん」 真剣なのかそうでないのか分かりにくい口調で、彼女は言った。「怖いわねえ」 デューラムは溜息をついた。「おまえ、本当に怖いと思ってないだろう」 「あら、思っているわよ」 クリッサはにこにこと、邪気のない笑顔で、 「とりあえず、幽霊撃退のための道具を色々持ってきたから、活用するといいわよ。まずこれはねえ、とねりこのステッキ。普通のステッキだと幽霊の体を通り抜けてしまうんだけど、樹齢三百年以上のとねりこだと、ばしんと打ち据えることができるんですって。それから、これはねえ、降霊術でやってきた幽霊が帰ってくれないときに、無理やり帰らせるための鏡。これに霊を映すことができたら帰ってくれるの。幽霊は鏡に映らないことも多いのが玉に瑕なんだけど……」 大きな袋から様々な品物を取り出しながらクリッサが際限なく説明を繰り広げるのを、デューラムは半分うわの空で聞いていた。昨日のようなたぐいの恐怖を、彼はこれまで味わったことがなかった。一人で森を歩いていて巨大な飢えた熊に出会ったとき、高い崖のきわで足を滑らせたとき、等々、死と直面する恐怖はこれまで何度か経験してきたが、昨日の夢は、狂気と奇妙な現実味の入り交じったおどろおどろしさがあった。 幽霊を目撃したほかの3人も、それが危険な存在らしいと感じているらしかった。自分の家で一人で寝るのは絶対によせ、うちに来た方がまだましだ、とダグラスとツァランは言うのだった。だから、結局イザクもまじえた彼ら四人は、ふたたび幽霊撃退の対策を練るべく市壁の中のダグラスとツァランの家に集合したのである。 クリッサを呼んだのはツァランだった。どこか間の抜けた印象のあるこの娘が、果たしてあの恐ろしい女に太刀打ちできるのだろうか、とデューラムは訝しんだ。だがツァランはあの幽霊に対処するすべを知っているのは仲間の中でもクリッサだけだと主張するのだった。ツァラン以外の3人は半信半疑だったが、だからと言って他に手があるわけでもない。ゆえに彼らはこの魔女見習いの力を借りることに決めたのだった。 「いや、色々あるのはまったく心強いんだがな」ダグラスが無精髭を捻りながら、 「その、ですってというのが気になるな。おまえさん、使ったことはないのか」 「いくつかは使ったことあるわ。全部じゃないけど……。それでも、お師匠様が太鼓判を押した『隠秘学大全』に書いてあったものばかりだから、大丈夫よ。きっと効くわ」 「きっと……」デューラムは不安げに繰り返した。 「そのとねりこのステッキは本当に効いたわよ」 クリッサは心外とばかりに目を見開いた。 「この間降霊術をやった時に、なんだか粘っこいのが来たの。お客さんが呼んでほしいと言った息子の霊にくっついて、なんだか鳥と人間が混じったような、変てこな霊が来ちゃったの。息子が帰ったあとにも居座っちゃって、そうしてなんだか人間の言葉が通じないらしくって、いろいろ除霊の文句を唱えてもちっとも動じないものだから、とうとうそれでばしんと打たざるを得なかったってわけなの。怖かったわよ、あんなの、はじめて」 「そりゃすごいな」 デューラムは少し感心し、その「とねりこのステッキ」を見つめた。どこからどう見ても変哲のない生木の杖だったが、そうした話を聞くと何やら神秘的な形状をしているような気がしないでもなかった。 「本当に効果があるのか——これ、借りてもいいのか」 「勿論!」 クリッサはにこにこした。「そのために持ってきたんだから。だけどね、忘れちゃ駄目よ。そいつを使うときには、出来る限り大きく天に向かってそいつを振り上げて、できる限りの大声で退散って叫びながら、霊をまっすぐ上から下に打ち据えるのよ。どたまを真っ二つに割る気持ちでね! 斜めは駄目よ。まっすぐよ! それを三回繰り返すの」 退散、とデューラムが弱々しく繰り返すのを見て、クリッサはかぶりを振った。 「そんなんじゃ駄目よ、ちゃんと叫ぶの。こうよ、見てて、いい?」 彼女はそのステッキを掴むと椅子から立ち上がり、誰もいない宙空に向かって大きく両手でステッキを振りかぶった。恐ろしげな形相できっと目を見開くと、退散、退散、退散と叫び、ぶんぶんと杖を振り回す。 クリッサを除く四人は顔を見合わせた。彼女のしぐさに迫力は感じられず、たちどころに幽霊を撃退する秘儀とはとても見えなかった。 「だけども、その霊、言葉が通じなかったって言わなかったか」 デューラムは小声で聞いた。「退散って言って何か意味、あるのか」 「あれっ、そういえばそうね!」 クリッサは、ぱっと顔を輝かせ、「なんで効いたのかしら? もしかしたらわたしの迫力に気圧されたのかもね」 デューラムは溜息をついてツァランとイザクのほうを眺めやった。ダグラスも同様だった。だが二人とも無表情に成り行きを聞いているだけで、何も意見を言おうとはしない。 「それから、今日ここに幽霊が出るといけないから、一応魔法陣を描いとくわ」 クリッサはさらに続けて、袋から黒っぽい液体の入った硝子の瓶と筆を取り出した。その液体は少し艶と粘りけのあるもので、彼女の手の中でランプの光を反射してどろりと光った。 「それは何だい。魔法陣を描くインクなのか?」 「そうよ、悪霊(あくれい)を閉じこめる魔法陣を描くためのインク」 クリッサは立ち上がると、ざっと部屋を見渡した。それから部屋の隅の一つに足を向け、長靴だの箱だの、本だの巻物だの、衣服の塊だの、堆積していた様々な物品を乱暴に脇にどけると、ここに描くわよと言った。 「まあ、別にいいけど」 と、ダグラスは不明瞭な口調で、「それ、ことが終わったら消してもいいのか? ……というより、消えるのか、そのインク」 「綺麗には消えないかもしれないわねえ、入っているものが入っているものだから」 「何が入ってるんだ」 クリッサは目をぱちくりさせてから、きゅぽんと音を立てて瓶のコルクを抜く。むっとする生臭さが、かすかに漂った。 「色々だけど、聞かないほうがいいわよ。男の人にちょっと抵抗あるかもしれないものも入ってるわ」 デューラムはその言葉に漠然といくつかの可能性を思い浮かべたが、はっきりとはわからなかった。とりあえずどれを使っているにせよ、清らかな何かとは程遠い代物であることは確かだった。 ダグラスが何やら呻く。クリッサはそうした反応を気にするでもなく、太い筆をインクに浸すと、黙々と床に魔法陣を描く作業を開始した。 「ところで」 しばらく黙っていたツァランが口を開く。「悪霊退散儀式のトレーニングは勿論のこと大事なのだが、他にもできることがあるように思う。——朝話したろう。情報の集約だ」 「そうだったな」 デューラムは今日何度目かの溜息をついてから、残りの三人を見やった。幽霊体験のあと、四人はそれぞれできることをもっと調べようということで合意したのだった。とにかく幽霊を怖がるにしても対策を立てるにしても、わからないことがその時点では多すぎた。 「誰からいく? ——ツァラン?」 「いいだろう」 ツァランが椅子をぎいと鳴らしてテーブルに両腕をつく。 「ぼくが調べたのはまず、あの幽霊が呟いていた内容の確認だ。昨晩、あの幽霊が何度も繰り返していた単語の中にぼくの知らないものがあって、気になっていたのだが」 「うん?」デューラムは先をうながした。 「また、だった」 「また、って」とダグラス。「もう一回ってことか?」 「そうだ。再び——また、また、——そういう意味の、方言だと思う。つまり、あの幽霊が言っていた内容はこうなる。愛しい人よ、あなたはまた死んでしまった。あの時の別れが最後だと思ったのに、もう二度と離れることはないはずだったのに、またわたしは一人になってしまった」 「また死んだ?」 デューラムは眉をひそめた。「一回死んで、また死んだのか?」 「そうなる」ツァランは腕を組んだ。「それから衣装だ」 「衣装?」 「あの女が着ていた服だ。このあたりで現在見られるものじゃなかったろう」 テーブルに着いていた残りの三人は顔を見合わせた。 「……まあ、古めかしい服だったような気がしないでもないが、なにより暗かったんでな」と、ダグラス。 「確かに暗かったが、シルエットは見えたろう。……知らないのか、衣装の時代とその性質を見分けるために重要なのは、服のラインだぜ。まあ、流行は数十年ごとに何度も巡るから一概には言いがたいが、わかることはたくさんある」 「おまえがそう言うんならそうだろうな。それで?」 「まず、全体的に飾り気の少ない、簡素なラインだったということが一つ、あの直線的なラインから察するに、あの生地はなめらかで柔らかい絹などではなく、厚くけばだった大衆的な生地だろうな。それにも関わらず、袖が先に行くに従って広がる形の上衣だった。これは近年もたまに見られるが、カフスで袖の先を絞っているものがほとんどだし、夜会服などで見られる場合は、もっと全体が飾りだらけの華美なラインになっているはずだ。 それから髪型だ。耳の前で編んだ髪が光っていたのを覚えている。前髪を編んで耳の前に垂らし、ひものようにぐるりと耳の後ろに回して頭頂付近に持ち上げて結う――これはこのあたりだと帝国統治が始まる頃までに広く見られた髪型で、かつ髪をスカーフなどで覆わず、露出させていることから考えると――」 「結論を言ってくれ」と、イザク。 いっぽう、ダグラスはしきりに感心している。「おまえ、服やら髪やらに詳しかったんだな! 女とも話が合うんだろうな」 ツァランはじろりとダグラスを睨みつけた。「すこぶる残念ながら、この手の知識が色事に役立ったことは一度としてないぜ。衣装風俗というのは歴史上の人々の生活を知る上で重要な情報なんだ。まあ、ぼくも今日帰ってから少し調べたというのが本当だがな——ともあれ」彼はそこでひとつ咳払いをした。「使っていた言語とも考え合わせると、あの女はおそらく、五百年から六百年前にこのあたりの農村に住んでいた貧しい未婚の女性だ。これはデューラムの夢の内容とも一致する」 「五百年から六百年!」デューラムは驚きの声をあげた。「けっこう昔だなあ」 「まあな。五百年より短くはない、それは確かなんだが」 ツァランは少し悔しそうに、「農民の生活文化は変化の早さに差があるので、それくらい漠然としかわからない。公的現場だと帝国語は七百年前にすでに話されていたはずだが——普通の町民や農民のあいだでは、その浸透具合も様々だからな」 「まあそれだけ分かれば上出来だよ」 デューラムは感心した。「じゃあ、次かな……イザク、おまえ、どこでこの花を見たか思い出したか」 イザクはデューラムの部屋に落ちていた花——現在は彼らの目の前のテーブルに置かれたその花を見ると、太い腕を組んだ。「ああ」 「どこだった?」 イザクは眉を寄せた。「おいデューラム、おまえこいつが咲いていたときを知ってるだろう」 デューラムは頷いた。「えーと……綺麗な青だったな。大きな花びらで、真ん中が白っぽくて、おしべが黄色の」 「ふん」イザクはさらに顔をしかめると、テーブルの上の枯れ花を持ち上げた。片方の手で、しなびた花弁の下あたりを指さす。そこには種が入っているのか、大きなふくらみが見えた。 「枯れてるからすぐにはわからなかったがな、このふくらんだ部分が特徴的なんで思い出した。こいつはな、よく大きな動物が死んだあとに生えてくる花だ」 残りの三人は目を見張る。 「たまに鹿や熊なんかの大きな死体を見たと思うと、何ヶ月かして死体がすっかり腐ってから、この花が生えてくることがある。だから、十本も二十本もこの花がぞろぞろ咲いているのを見たときには、ああ、そこで何かでかいのが死んだんだな、とそう思うわけだ」イザクは頭を掻いた。「綺麗な色をしてる綺麗な花だけどな、よくでかい肋骨がむきだしになってるその真ん中に生えていたりして、不気味ではあったな」 ツァランが席を立った。居間を出て階段を上っていく。しばらくして戻ってきた彼は、両手に何やら分厚く巨大な本を手にしていた。なんだそれ、と聞いたデューラムに、ツァランは植物図鑑と答えた。 「植物図鑑って、おまえ簡単に言うけど」 デューラムは驚き呆れて目を見張った。「……そんな高価なもの、なんで持ってるんだ」 図鑑——学者の高度に専門的な知識と、名のある細密画師の手になる特別な書物である。彫りの粗い木版を用い、質の悪い藁半紙に印刷された大衆浪漫や滑稽劇なら、書物とはいえ道ばたでも二束三文で手にはいるが、緻密なスケッチが必要な図鑑となるとそうはいかない。そのほとんどは細密画師が直筆で絵を描いたもので、したがって値段は目が飛び出るほど高いはずだ。図書館などに行くこともないデューラムは、じっさいに触れたことすらない。一度、めったに足を踏み入れることもない高級商店街の古道具屋の窓際に、頁を開いた状態で鎮座しているのを外から見たことがあるだけだ。それはたしか人体のしくみについての図鑑だったか——気が遠くなるほど細かい線の絵で心臓だの肺だの血管だのの様子がしるしてあるその頁に、デューラムはおどろおどろしさを通り越して崇高なものすら感じたほどである。 ツァランは肩をすくめた。「たいして貴重なものじゃない。こいつは一般に言うところの俗悪本だからな。以前写本の仕事をした図書館で、価値のない本として転がってたのを、仕事の報酬がわりに貰ったのさ」 「そんな俗悪本を信用できるのか」 「できる」 ツァランはどさりとテーブルに図鑑を置いた。相当な重さと見えた。「こいつが俗悪本になったのは、執筆した学者が失脚したという、ただそれだけの理由だからな。この世の真理なるものはいつでも政治がらみだが、図鑑程度の基本情報なら比較的時流に関係なく信頼できる。それはそれとして——花の名は知らないだろうな、イザク」 「知らん」イザクは肩をすくめた。「ただおれたちは魂吸(たます)い花と呼んでたな」 「方言索引に載っているかな……」 ツァランは何やらその本の後ろのほうを調べ始めた。デューラムが少し覗いてみると、そこには目の痛くなりそうなほど小さな字で膨大な数の呼び名がページいっぱいに羅列してあった。いくつかあるな、とツァランが言いながら、ページのひとつを開く。きわめて細密な線で描かれた花のスケッチのひとつを指さし、「こいつはどうだ、デューラム。マーヤがくれたのはこの花か?」 「いや、違う」デューラムは首を振った。 「たしかにこいつは赤い花だと書いてあるな。じゃあ次はどうだ」 ツァランは図鑑の別のページを重たそうに開いた。「——こいつは?」 デューラムは目を見開いた。「ああ……これだ。たぶんこれだ」 そこに描かれていたのは、たしかにデューラムが部屋に飾っていたその花の、満開の時分の様子だった。先の尖った五枚の大きな花びらが放射線状に伸び、中央に小さなおしべが覗いている。葉も大きく、すっとなだらかに伸びた流線状のラインを描いていて、優雅で可憐な花だった。マーヤがこの花を持ってきたとき、確かにデューラムは思ったのだ。ああ、本当に綺麗な花だな、と。 「二本……二本咲いてたと、そう言ってた」 「この花がか?」と、ツァラン。 「うん」デューラムは顔を撫でた。 「マーヤがそう言っていた。森の小さな崖のふもとに、二輪並んで咲いていたって。あんまり綺麗だから、一輪残して、一輪だけ摘んできたと」 「二輪か」ダグラスが呻く。 ツァランがスケッチの横の、やはり微細な説明文を指でなぞった。 「ああ、確かに中・大動物の遺骸を養分としてよく育つ花であると書いてあるな。大きな戦のあとにも繁茂するため、魂吸いの花、あるいは兵肉食いの花という異名で呼ばれることもある……」 そう言って、ツァランは目を細めた。「……デューラム、飾っていた花が枯れたのは最近か?」 「ああ」デューラムは低く答えた。「しばらくは綺麗だった。完全にしなびたのはせいぜい二日前か、昨日だと思う」 四人はしばらく、黙った。……物語が線を結びはじめていた。 「五百年とか六百年前に、このあたりで大きな戦ってあったのか?」 デューラムの問いに、ツァランは眉を寄せてううんと唸り、「いくらでもある、とは言えるな。あの森が戦場になったのがどれだかはちょっと思い出せないが」 「だがそういうのは騎士とか、そういう偉いのが戦うんじゃないのか?」 ダグラスの問いに、いや、とツァランはかぶりを振った。「兵の大半は、なんの訓練も受けていない農夫——いや、農奴だな。普段は領地で畑を耕してる農奴を戦のときにだけ引っ張り出して、それで農奴たちはおたがいなんのための戦かも知らず、それぞれの領主のために殺し合いをさせられる。そんなものだ。言っておくが、今だって多くの地域ではそうだぜ」 「……しかし」 デューラムは食い下がった。「毎年毎年、枯れては咲き、枯れては咲きをくりかえしてきたっていうのか? 数百年も前に死んだ農奴の死体を養分に? 馬鹿げてる——その死んだ農奴の肉だの血だのだって、数年もたてばすっかり土じゃないか!」 ふむと呟くとツァランはぱたんと図鑑を閉じた。「幽霊が何百年の年月を超えてこの世にさまよい出るのなら、その情を宿した一本の花だって何百年ものあいだ咲きつづけるかもしれないぜ」 「そんな……」 馬鹿な、とデューラムは言おうとした。だが、幽霊が確かに目の前に姿を現したという事実の前には、どんな突拍子もないことだって、ありえないとは言い切れないのだった。 ふたたび落ちた沈黙を破ったのはクリッサだった。「なんだかしんみりしているようだけど」 いつ魔法陣を描き終えたのか、いつから彼らの話を聞いていたのか、彼女はインクの瓶を袋にしまいながら言った。「話を聞いてるかぎり、その幽霊、今日もきっと出てくるわよ。気をつけてね」 デューラムはぎょっとした。 「だが、ここはおれの家じゃないぜ」 「でも、その花がここにあるじゃない」 クリッサはテーブルの上の枯れ花を指さした。「おとついここに泊まったときには、その花デューラムの家に置きっぱなしだったんでしょう? だから出なかったのよ。今日はわけが違うわ」 デューラムは呻いた。 クリッサは壁に掛けられていた自分の外套に手を伸ばしながら、 「いい、情にほだされちゃ駄目よ。亡霊っていうのは、可哀想だなあとか、淋しいんだろうなあとか、そういう感情につけ込んでくることも多いのよ。それでひょいと誘われていっちゃう人が後を絶たないんだから。 ……昨日、デューラムは死ぬかと思ったんでしょう? そんなに攻撃的な亡霊なら、いずれデューラムを引き込もうとするかもしれないわよ」 「冗談だろ」 デューラムは悲鳴をあげた。「なんでおれがそんな目に!……いや待てクリッサ、まさか帰るつもりか」 じっさいクリッサはすでに外套を着ていて、テーブルに広げたいくつもの道具を袋にしまい始めたところだった。 「今日は駄目なの、用事を残してきちゃって——あれ明日の朝までにやっとかないと、お師匠様が怒髪天を衝くのが目に見えてる」 「そんな薄情な」と、デューラムは我ながら情けない声だと思いながらも、「頼むよ、一晩いてくれよ。このなかで一番亡霊に詳しいのはおまえなんだ」 だがクリッサはにこにこと笑うばかりだった。「ごめんね、駄目なの。でもそのとねりこのステッキと、ほかにもいくつか置いとくから。大丈夫、大の男が四人も揃ってるんじゃない!」 「男ってのは相手によっちゃあ束になってもまったく無力なもんでな」 ダグラスが重苦しく言う。「数百年前に死んだ女の怨念なんてその最たるもんだ」 「大丈夫よ、きっと!」 からからと笑う。まったく根拠のない台詞に聞こえた。 クリッサは外に出るドアを開けながら振り返ると、きゅっと真面目な顔になって言った。 「いい? 幽霊が出たら完全に撃退するのよ。変な同情はしないで、そのステッキで、ばしん、ばしん、ばしんと三回、いいわね」 そうしてクリッサは帰っていった。 三人はおたがいの表情を見比べた。 「なあ」とダグラス。「あの幽霊、昨晩な、最後に振り返ったろう」 「言うな」と、イザク。 「なんだ?」デューラムは動揺した。「おれは寝ていたから……いったいなんだってんだ。振り返ったらどうなってたんだ?」 「おれも知らんのだ」ダグラスが水を一口飲んで言う。「とっさに目をつぶっちまった」 「ぼくはちらりとしか見ていないが」と、ツァラン。「いや、デューラム、きみは知ってるはずだ。夢の話で言っていたからな」 デューラムは眉を寄せた。「夢でなんか、何を……あ、」 そこで彼は思い当たった。「……目が」 「言うなというのに」イザクが溜息をついた。「思い出させるな」 「なんだ?」と、ダグラス。 「両目がどろっと」デューラムは呟いた。「溶け出してたんだ」 <<< 5 >>>
|