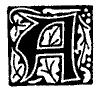 CHILLING DREAM. CHILLING DREAM.ダグラスがふと目を覚ましたのは、真夜中のことだった。 一瞬、自分がどこにいるのか思い出せなかった。いつも寝ている寝台の上ではない、何か妙にやわらかいものの上に自分は横になっていた。びくりと起きあがりかけたところで、彼は自分の置かれた状況を思い出した。右と左に転がる人影を、彼は暗闇の中でイザクとツァランと見分けた。 イザクの鼾が聞こえる。 そうだ、藁の上で寝たのだった。 その夜、酒盛りをほどほどのところでお開きにして、彼らはデューラムの小さな寝室に移ったのである。寝台は一つしかないから、デューラム以外の三人は床の上に藁をしき、それに布を被せた上に雑魚寝をすることになった。ほろ酔い加減になっていた彼らは、だがそんな簡易な寝台の上でもすぐに寝入ってしまったのである。 月が出ているのか、窓からわずかに夜の光が差し込んでいた。ベッドに目をやると、こちらに足を向けて横たわるデューラムの影が青い薄明かりのなかにぼんやりと見えた。イザクのものより小さな鼾が聞こえた。彼はぐっすりと眠り込んでいるようだった。 (やっぱり夢でも見たのかな、やつは) ダグラスは苦笑した。幽霊譚を完全に信じていたわけではないが、それでも拍子抜けしたような気分だった。デューラムは物事を大げさに騒ぎ立てるたちではなかったので、ひょっとしたらとダグラスも思っていたのである。 (まあ、農夫にゃあ忙しい時期だしな、疲れてたんだろう) ダグラスは大きな欠伸(あくび)をした。ツァランが寝返りを打つ気配がして、ごとんと小さな音がした。 それにしてもみんなよく寝ている。寝ずの番をするなどと言っていたのに、結局誰一人として起きていられなかった。 彼は苦笑して、自分もまた寝入ろうと目を閉じた。 そこで違和感がした。 ――なんだ、今の音。 もう一度ごとんと音がした。さっきのツァランの寝返りの音――床が鳴る音だ。靴音のような……いや、違う。寝返りじゃない。ダグラスは目を開け、足下に目をやった。そこには三人が寝る前にめいめい脱ぎ散らかした靴が転がっていた。 彼ら三人のうち誰かが立てる靴音であるはずがないのだ。 ごとん そしてその音は確実に、部屋の中から響いていた。 ダグラスはごくりと唾を飲んだ。手を伸ばし、左隣のツァランを二、三度ゆする。だが相棒は完全に熟睡していてまったく起きる気配を見せない。ダグラスは舌打ちし、もう片方の手でイザクを揺さぶった。 こちらの目覚めははるかに良かった。イザクは低く呻くと目をこすった。「なんだ、鈍牛……」 イザクは凶悪な声音で言ったが、直後にびくりとして上体を起こした。 ごとん、ごとんと小さな音は続いている。そうしていまや、ダグラスが注意を向けているものはその足音だけではなかった。イザクがダグラスの見ている方に向き直り、低く呻く。その呻きで、ダグラスはイザクが自分と同じものを見ているのを知った。 女だ、とダグラスは思った。彼らが寝ている部屋の隅とデューラムの寝台の真ん中に、女が立っている。 だが、はっきりとその姿形を認識したわけではない。なにしろ月の光が窓から差し込むだけの暗闇である。家具も壁も何もかも、ぼんやりとした線と影の交錯でしか確認できない暗闇である。その中に立つ人影に、彼はただ細い肩の線を認めた気がしたのだ。そして波打つ長い髪がかすかに月にきらめくのを見た気がしたのだ。……人影はさして広くもないデューラムの寝室の、中央から窓際に向かって、そして窓際からまた中央に向かって、ひどくゆっくりと歩いているようだった。 ダグラスは腕を伸ばして思い切りツァランの腕をつねった。ツァランは呻いてこちらを向いた。何やら寝ぼけた台詞を小さく呟く。ダグラスは部屋の中央にむかって顎をしゃくってみせた。 ツァランはまだ頭が眠っているのか、そのしぐさの意味をはかりかねているのか、しばらくぼんやりとダグラスの顔を見ていたようだった。それから彼が向く方向を追うように、ゆっくりと振り返る。ツァランが息を呑むのをダグラスは感じ取った。 女は窓際に置かれた机のすぐそばに立っていた。それはこちらに足を向ける格好で寝ているデューラムの、ちょうど頭の横の位置だった。 そうして溜息が聞こえた。 長い長いその溜息は、慟哭を混じえたように震えながら消えた。女はゆっくりとデューラムのほうに向き直ると、寝ている彼をじっと見下ろした。相変わらずそのシルエットを漠然と捉えることしかできなかったが、ダグラスは女にどこか土臭い、古めかしい印象をおぼえた。そうしてその横顔の、額から鼻にかけての線のすぐ下で、一筋何かが光っていた。頬の線だと彼は思ったが、何故だかぞっと鳥肌が立った。その光はどこかぬらりとしていて、薄気味悪いものに思えたのである。 デューラムが呻いて寝返りを打った。うなされるような声だった。さらにはその呻きに混じって、呟きのような声が聞こえていた。それは女の声ではあったけれども、あまりに低くしゃがれており、そのためかどうかダグラスにとってはまったく意味のとれないものだった。 呟きは次第に大きくなる。何だかわからないが、すこぶるいやな予感がして彼は歯がみした。今すぐ飛び出してデューラムを起こさねばならない、あの女をなんとかして追い払わねばならないと思った。だが、何故だか体がひどく重たいのだ。彼の隣の仲間ふたりも、動く様子ではない。驚愕に目を見開いて、眼前の現実とも知れぬ光景を食い入るように見つめているばかりである。 さらに、デューラムの声は少しずつ苦悶のそれになっていく。「……嫌だ……」意味をなさない寝言のなかに、その言葉が混じるのをダグラスは聞いた。デューラムは苦しげに首を振り、毛布を掻きむしった。「……やめろ……」 かたや女の呟き声はどんどん大きくなっていった。いまやそれが異国の言語であるのがはっきりとわかった。そうしてその呟きには、この世のものとも思えぬまがまがしい怨恨の響きが濃厚に絡みついていた。ダグラスは唾を飲み、手を握りしめた。 やめろ、やめろ、もう消えろ! そのとき、女ががばりとデューラムに覆い被さった。同時にデューラムがつんざくような恐怖の叫びをあげる。ダグラスは目を見開き、全身に渾身の力をみなぎらせると、猛獣のようなうなり声をあげてとうとうその場に飛び起きた。 彼は吠えた。「消えろ!」 次の瞬間、その声に弾かれたようにツァランが起きあがり、何かを女に向かって投げつけた。女がこちらを振り返る――ダグラスは思わず目をつぶった。 そうして、叫びが 一瞬、意識が飛んでいる。 目を閉じていたせいかもしれない――気がつくと、彼は部屋の中央あたりで立ちつくしていた。ツァランが背後で荒い息をついている。 女は消えていた。 部屋の中にはただ、青白い月の光が静かに差し込んでいるばかりである。 イザクが飛び起きてデューラムのベッドに駆け寄った。彼はデューラムの名を叫びながら、その体を揺さぶった。 「起きろ! 起きるんだ!」 デューラムは苦悶の呻きをあげた。ダグラスはイザクに続いてその側に駆け寄った。イザクに何度か頬を叩かれて、デューラムはようやく目を開けた。 ダグラスは安堵の溜息をついた。「大丈夫か」 「うん、ああ……」 デューラムは汗だくだった。ベッドの上に起きあがってぎゅっと目を瞑ると、その額から雫が頬を伝った。「夢か」 「いや、夢じゃ……」ダグラスが言おうとするのを、イザクが手を挙げて制する。 ツァランが床から何かを拾い上げる。先ほど彼が女に投げつけたものだ。 そして一輪の花。 「おれはどこか村にいる。……でもなんの見覚えもない景色なんだ。家はどれも粗末で、小さくて、石じゃなくて木でできているものもたくさんあって……何人か人が歩いているんだけれども、みんな顔に見覚えもない。服もずいぶん古めかしくて、質素だった。みんなぼんやりした顔をして、ぼんやり動いているんだ。老人と、子どもと……女ばかりだった。 「いつのまにか村の広場みたいなところにいる。あたりの家々はやっぱり粗末で、窓から痩せこけた子供の顔がいくつも覗いてる……みんなぎらぎら目を光らせているんだ。広場の中央には背の高い石版が——石碑が立っている。何か金色のものがそこでゆらゆら揺れてる。それは人で、人の髪の毛なんだ。長い金髪を振り乱した誰かが、そこで石碑に向かって何かしてるんだ。手が真っ赤で……何かを引きはがそうとしてるんだ。おれは逃げたいんだけれども、目のぎらぎらした子供が寄ってくるので、歩けない。歩くとそいつらを踏みつぶしてしまうからだ。女が、こっちを見て……なにか目から垂れ下がっていて、そうしておれに向かって手を伸ばすんだ。その指から爪が剥がれて先っぽでぶらぶら揺れていて――おれの顔に」 デューラムはそこで息をついた。「そうして目が覚めた」 沈黙が落ちる。 四人はふたたび居間に移動してテーブルを囲んでいた。夜は大分更けていたが、それでも夜明けはまだずいぶん先だった。デューラムは一度火勢の弱まった暖炉にもう一度薪をくべ、また見つけられる限りのランプに火をつけていた。だがそれでも家の中はまだ薄暗く、凍えて感じられた。 「その夢は、これまでも毎日見てたのか」 ツァランの問いに、いいや、とデューラムは答えた。それは今日初めて見た悪夢だった。 「いままでは足音と溜息だけだったんだ。死ぬかと思ったのは今日が初めてだな」 「実際なあ」ダグラスが呻いた。「おまえが殺されるんじゃないかと思ったぜ」 ふたたび重苦しい沈黙が落ちる。 イザクが席を立った。台所から水差しと人数分のカップを持ってくる。彼は自分の分を注いで、再び席に座ると唸った。「いったい今日、何をしやがったんだ、おまえ」 「何もしやしないさ!」 デューラムは憤慨し、「だいたい昨日も今日もほとんどおまえらと一緒にいるんだぜ。何をしたかはだいたいおまえらが知ってるだろう」 言いながら、デューラムはイザクの差し出したカップを受け取り、一気にあおった。ただの水がひどくうまく感じた。 「あれは何を言ってたんだ?」と、ダグラス。 あれ、というのは女のことをさすのだろうとデューラムは推測した。彼もまだ足音しか聞いたことのない幽霊の姿を、この三人は見ているのだ。 「……東邦語の一つだと思う」そう答えたのはツァランである。 「東邦語?」 「このあたりで帝国語がずっと昔から使われていたわけではないからな。東邦語は帝国語が一般的になる前にこのあたりで使われていた言語だ」 ダグラスが目を剥く。「おまえ、わかったのか、内容が」 「わかった……のかどうか怪しいがな。そもそもぼくは東邦語をあまりよく知らない。種類も多いしな。実際に話されるのを聞いたことはほとんどないから、あまり自信がない」 「自信がなくともわかったんだろ。まったくのちんぷんかんぷんよりゃましだ」 ツァランは眉を寄せたが、唇を舐めると、躊躇をふくんだ声で言った。「……ぼくの聞き間違いである可能性も高いが、あれは恋人への別れの句のようだった」 「恋人?」 「そうだ。恋人よ、あなたは死んでしまった、あれが最後の別れだった、わたしは一人だ、とか……そんな内容だな」 「ふむ」ダグラスは腕を組んだ。「誰が恋人なんだ? デュールか?」 「おれはまだ死んじゃいない」デューラムは当惑した。「それにそんな言葉を幽霊に向けられるおぼえはない」 「愛しい人よあなたを連れて行こう、だったらまだわかるんだが……。幽霊はよく『呼ぶ』というしな。だが、『あなたは死んでしまった』、だ。腑に落ちない。だから自信がないと言ったんだ」 そうツァランが言ったのを最後に、四人は黙りこくった。昨晩までのどんちゃん騒ぎじみた空気は完全にぬぐい去られていて、みな陰鬱な顔つきをしていた。幽霊は確かに出たのだ。しかも、それはどうやら危険な存在らしかった。もし三人が今日来ていなかったら、自分はいったいどうなっていたのだろう。デューラムはぶると身を震わせた。考えたくもなかった。 「しかし、おまえ最後に何を投げたんだ?」 ダグラスに問われ、ツァランは肩をすくめた。「ヒイラギさ。だがあれが効いたのかどうかはわからない。単純におまえの吠え声に圧されて退却したのかもしれん。あるいはデューラムの悲鳴に驚いたのか……クリッサにでも聞かないとわからないな」 クリッサとは、やはり彼らの仲間の一人である魔女見習いのことである。彼女はその魔法使いの師匠のところで、魔法の修行と名うたれてはいるが実質雑用と家事一般のようなことをしながら暮らしていた。 「だがあの化け物屋敷の話もあるじゃないか」 「あれはただのお話さ。半分以上は誰かの創作だ」ツァランはにべもなく、「おまえの話したバージョンですらな」 また嫌な沈黙が落ちた。 ツァランは溜息をつくと、懐からヒイラギを取り出した。「お守りはいかに効能が怪しくともないよりはあったほうがいいが、これだけではまったく心許ない――」 「おい、そいつはなんだ」 イザクだった。その手がツァランの手から床に落ちた何かを指さしている。 ああ、といま気づいたかのようにツァランは言うと、それを床から拾い上げてテーブルの上に置いた。しなびた一本の茎、否、枯れかけた花とおぼしきものだった。デューラムは思わずあっと声を上げた。 「寝室に落ちていたんだ、ぼくが投げたヒイラギの隣に……なんだデューラム。なにが『あ』だ」と、ツァラン。 「なんでもない」とデューラムは口元に手を当てた。しかしその様子は残り三人の疑念をむしろ高めたようだった。三人に口々に詰問されて、デューラムは観念した。 「それはマーヤにちょっと前にもらったんだ……おかしいな、でも瓶に差して机の上に置いておいたはずなのに」 「なんだ、のろけ話か!」と呆れたようにダグラス。「しかしそいつはもう枯れてるぜ。捨てがたいというのはわからないでもないが」 そういうわけじゃない、と言ってデューラムは顔を赤らめた。「おれは花のことなど知らないから、いつ処分するものかわからなかっただけさ」 「そうかもしれないが、これはさすがに完全に——」 花を持ち上げてそう言ったツァランは、そこで言葉を止めた。「……デューラム、あの幽霊は十日前から出始めたと言ったか」 デューラムは突然の質問に困惑した。「そのくらいだな」 「マーヤがこの花をくれたのは?」 「いつだったかな……それも十日くらい前かな」 デューラムは思い出そうと顔をしかめてから、はっとした。「おまえ、つまり」 ツァランは答えなかった。花をテーブルの上に戻すと、腕を組む。 「なんだなんだ、あの女は花の精だとでもいうのか」と、ダグラス。「とてもそんな可憐なものには見えなかったぞ!」 ツァランはため息をつくとかぶりを振った。 「わからない。だがほかに手がかりがないと言えばないからな。……どうした、イザク」 イザクは無愛想な顔をさらにしかめっ面にして、身を乗り出すようにして花を見つめていた。ツァランに問われ、うんと言って目を上げる。 「いや」無口な男はそう唸り、呟くように一言だけ言った。 「こいつは、どこかで見たな」 |