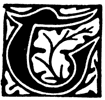 HE FELLOWS. HE FELLOWS.どんと音を立てて木製のテーブルが揺れた。同時に目の前に置かれたジョッキから泡が溢れて、テーブルの上に水たまりをこしらえる。 「おっと!」 デューラムは慌ててジョッキに口を付け、なみなみと揺れるエールを啜った。「こぼれたじゃないか……乱暴に置くなよまったくもう」 「気に病むな、青年。今こぼれたのは所詮泡、うたかただ」 そう言ったのは、彼の右隣に腰掛けた人物である。薄い唇のきわにかすかに皮肉めいた皺を刻んだその男は、もうひとつのジョッキに口を付けると眉を寄せ、続けた。 「波間のうたかたを気にしすぎると大洋が見られなくなるとは古い文士の言葉でな、たとえばこの例で言えば今日のエールの気が抜けかかっていて何やら間の抜けた味がするというのが大洋であるわけだ。いずれにせよ、おまえも動作をもう少し繊細にしろよ。さもないと家から叩き出すぞ、ダグラス」 「おまえこそ一日中無駄なことばかり呟いているその舌を止めんと、しまいにそいつをペンチで引っこぬくぜ」 ジョッキを運んできた巨漢の男がそう返した。いたずらっぽく茶色の目を光らせながらデューラムの真向かいにどっかりと腰を下ろす。簡素なつくりの椅子が彼の体重にぎいぎいと悲鳴をあげた。「なんていったか、嘘つきの舌を引っこぬく悪魔がいたろう」 「知らん」 デューラムは憮然として言った。「だけどもいまこの瞬間にその悪魔にご登場願ってこいつの舌を引っこ抜いてほしいよ! ……ところでダグラス、椅子を壊すなよ。おまえこのあいだ酔っぱらって一つおしゃかにしただろ。またでかくなったんじゃないか?」 「いやあ成長期はもうだいぶ前に終わったと思うんだが」 と、無精髭のあごを撫でたダグラスは、実のところかなりの大男である。身長は六フィート(注:180センチ強)をゆうに超えており、体全体に筋肉がついて迫力のあるシルエットだ。首筋も肩も腕も胸板もがっしりと力強い。 しかしながらダグラスの堂々たる体躯も、この酒場《まだらの竜》にあってはとくに目立つものでもない。さほど大きくもない酒場は今日もほとんど満杯だったが、店を埋め尽くす客は体つきも雰囲気も千差万別で、あらゆる髪の色、肌の色、服装の輩がたむろしているのだった。共通点といえば、どの集団も個人も地位のありそうな雰囲気をたたえてはいない、ということだけである。 そもそもが市壁の中でも品の良くない通りに面する店だ。木と石が裸に露出した内装は、ある種の伝統を醸し出していたもののけして洗練されてはいなかったし、質素なテーブルと椅子はどれも歪んでいてがたがたと揺れた。店内には奥の台所から溢れてきた竈の煙と、酔っ払いたちの汗くさい体臭が充満していた。光の届きにくい隅っこのテーブルでは、若い男女が良識を超えた程度でいちゃついていたし、もうひとつの隅っこでは二十歳にも満たない若者の集団がひそひそと笑い合いながら、よからぬ白い粉を料理に振りかけていた。 いずれにせよ酒場に満ちた雰囲気は「何でもあり」としか形容しようのないもので、その意味でこの店はどんな背景をもつ人間にとっても開放的だった。そうしてデューラムらのように、それぞれが異なる出自を持ちながらもこの地に流れ着いて縁を持ったグループにとって、この《まだらの竜》のような場所は居心地がよいのだった。 要するに、デューラムが憂さ晴らしとして選んだのは仲間と自棄酒を飲むことだったのだ。酒を飲んだところで睡眠不足が解決するわけでも台無しにした肥料が回復するわけでもなかったが、気の置けない仲間とだべってでもいないとやっていられないというのが彼の正直な気持ちだった。そうしてその自棄酒で、ここ数日の肌寒い恐怖を追いやってしまいたい気分もあった。 「……つまりそいつは地獄で死人(しびと)の審判をしているわけだ」 隣の男がそう言うのを耳に挟んで、デューラムは意識を仲間内の会話に戻した。どうやら舌を引っこ抜く悪魔の説明らしかった。 ダグラスがふむと唸った。「しかしいまに始まったことじゃないが、おまえは役に立たなそうなことばかりよく知ってやがるな、ザラン!」 「ザハラーン」 ザランと呼ばれた男は、余人には真似しがたい、喉の奥に空気を絡めた複雑きわまりない発音で言い直した。 「でなければツァランと呼べと何度言ったらわかるんだ、そのうろんな鈍牛頭は? ついでに異議を唱えておくが、おれの知識はこのうえなく現実的なものばかりだぞ」 「鈍牛の脳みそにはおまえの名前なんぞのための余裕はないんでね」 正された方は気にする様子もない。「それに地獄の大王のどこが現実的だってんだ」 「それは一般教養というのだぜ。一般教養すなわち表層的・刹那的な実利に囚われることなくひとの人格ならびに世界観に深みを与える芸術的知識であり、その効能において結局きわめて実用的な知と言える」 「どうだっていいが、もうすこし短くものを喋れないのか?」 にぶい金髪の下からのぞく土気色の顔を、デューラムは睨みつけた。ツァランはとにかくよく喋る。いちおう王立図書館で働く学士であるから、その知識も思いつきではなく、確かなものなのであろうが、それにしては内容も語り口も胡散くさい。 「おれだっておまえみたいに一日中喋っていられたらと思うぜ。そうしたら鬱々と思い悩む暇もなさそうだ!」 「おや……、いったい何を悩んでいる、青年。今年の天気か? はたまた昨今ますます不穏になる政治動向か? いや、違うな」 ツァランはデューラムに人差し指を向けた。「さては恋だろう」 デューラムはツァランの指を押しのけた。もう一度エールのジョッキを煽り、口元についた泡を手の甲でぬぐう。「そんなんじゃないや」 失笑したダグラスの表情を見て、デューラムは自分の口調の子供っぽさに気づいた。さらに憮然として言い直す。 「いや、そんな事じゃない」 「じゃあ何だ」と、ツァラン。 デューラムは言いよどむ。この面子を前にして幽霊実体験談など到底話せるようには思えなかった。やれ起きても夢ばかり見ているだの、いったいどこで死後にも祟られるような悪行をやらかしたのかだの、ひとしきりからかわれた挙げ句にまともに取り合ってもらえないのがおちである。 「やっぱりその、恋なのか?」 黙り込んでしまったデューラムを見て、ダグラスが顎をさする。「その、なんて言った、ほらおまえの家の隣に住んでる娘がいたじゃないか、おまえこの前までちょっと気にしてたろう……あの娘とは最近どうなんだ、ちょっとは進展したのか」 「マーヤだな」ツァランが頷いた。 「可愛らしい娘ではあるな、何よりきびきびした印象があるのがいい。そばかすが少し気になるが、まあ、あの年頃だと若々しさの象徴で魅力でもある。あと綺麗な色の髪をしているな」 デューラムはぎょっとしてツァランを見た。「おまえ、マーヤをよく知ってるのか」 「ほう?」ツァランは意地悪く笑った。「気になるか」 デューラムはぽかんと口を開けた。「市壁のなかに暮らしているおまえが、いったいどうやってマーヤと会ってるんだ。まさか彼女が街に来るたびに会う約束でもしてるのか」 ツァランは答えず、意味ありげに眉を上げてダグラスにちらりと視線をやった。ダグラスはそれに応えてぱちりと目配せをすると、興味深そうに身を乗り出してきて、 「まあ……そう熱くなるなよ、デューラム。とりあえずいい娘だって評価を得てるんだ」 「じゃあ、やっぱり会ってるのか!」 デューラムがダグラスの言葉になかばあっけに取られ、なかば憤慨してさらに問いつめようとしたところで、助けは別方向から来た。 「そのくらいにしとけ、おまえら、やり過ぎだぜ」 呆れはてた口調で言葉が続く。「おい学士、おまえは口ばっかり達者だが、じっさいの所ろくに外にも出ずに建物の中で本ばかり読んでるんだろう。デューラムの知り合いと会ってる甲斐性なぞないだろうが」 それはデューラムのもう片方の隣に座っていた男だった。いままで黙りこくっていたその人物のことを、べつに三人は忘れていたわけではない。ただ彼は至極無口で、喋りたいとき以外は通常、何を聞かれてもうんとかああしか言わないので、みな彼に無理に話をふることもなく過ごしていただけである。 ツァランは肩をすくめた。 「ご明察だ、イザク。マーヤのことは、一度ちらっと見たことがあるだけだ。ぼくがデューラムの家を訪れた日にちょうど彼女がやってきて……覚えてないのか? よほど舞い上がっていたんだな、デューラム」 「ああ、あれか。なんだ……いや、べつに舞い上がってなんか」 デューラムはぼそぼそと口の中で言い訳をしてから、感謝を込めてイザクの顔を見た。年齢のわりには少しいかつく、いつも通りどこまでも無愛想な表情である。だが、こうしてダグラスとツァランの悪だくみが過ぎるようなとき、イザクはここぞという場所で助けを出してくれるので、デューラムにとってはありがたい存在なのである。 「とりあえず、その様子だと劇的に関係が進展したわけでもなさそうだな」 ツァランが愉快そうに笑う。 「まあこれもきみの恋路を心配してのことだ、悪く思うな。おわびに一杯おごる」 まったく反省した様子もなくそう言うと、ツァランはカウンターのほうに歩いていった。 「で、悩みというのは結局なんなんだ」と、ダグラス。 デューラムはため息をついた。例の話をすれば法螺吹き呼ばわりされるかもしれないが、繊細な人間関係を興味本位でいじられるよりは、まだましに思えた。 「……夜に足音がするんだ」 デューラムは自分を悩ませる不審な物音のことを、ぼつりぼつりと喋った。金縛りにあったように体が動かせず、足音と衣擦れの音と溜息が聞こえ、もうそれが何日も続いていると。 その話を目を丸くして聞いていたダグラスは、顎の髭をひねりつつ(癖なのである)、「それは、つまり……、幽霊ってことなのか」 「信じたくはないけどな。だが泥棒なら何日も何日も足音と溜息だけ聞かせる道理はないだろう?」 デューラムはエールをぐいと煽り、長く酒臭い息を吐いた。 「顔を見ることさえできないんだ。生きた人間か幽霊か、確かめる手段もないさ!」 「どっちの可能性もあるな」と、いつのまにか戻ってきていたツァラン。 「きみはいい奴だが、たまに鈍感だから、どこで恨まれているか知れたもんじゃない。いい奴というのは不条理な逆恨みを買いやすい、というのも事実だし」 「じゃなければ、さっきの娘、なんと言ったか、ええと、」 ダグラスが固有名詞の覚えの悪さを露呈しながら、「その娘がデュエルに想いを寄せて、毎晩寝顔を見に来てるんじゃないのか?」 「大口を開けて涎でも流した顔を見れば百年の恋も一気に冷めようというものだが、まあ恋は盲目とも言うしな。……しかし、なるほど、夜這いか、いやけっこうなことで」 最後にそう小さく付け加えたツァランは、デューラムに凶悪な視線で睨まれたので、肩をすくめて黙った。 「ふうん、じゃあこういうのはどうだ」と、ダグラス。 「おれたちがおまえの家に泊まりこんで、足音の正体を確かめてやるよ。四人集まればその不審な輩も問題なく捕まえられるし、いずれにしてもおまえだって、その足音の正体を知りたいんだろう?」 「面白い。どうせ最近は退屈していたところだ。いい景気づけになる」と、ツァラン。 「明日の夜はどうだ。今晩はぼくらの家に泊まるんだろう、二人とも。もうカリャンスクに帰れる時間じゃないぜ。森ならなおさらだ」 彼の言った森とはイザクの住居のことである。普段は木材の細工や家具を作って生計を立てている彼は、カリャンスクの端の森のそばにひっそりと暮らしていた。いっぽう、ダグラスとツァランの二人組は、ろくでもない企みが大好きなことで意気投合していて、市壁の中の一軒の家にむさくるしく同居していた。 デューラムは場の急展開に目をぱちくりさせ、どもりながら承諾した。あれだけ自分を虚仮にしたくせに、結局のところは二人とも興味津々なのだ。 「……おまえも来るのか、イザク」 「どっちにだ。おまえの家かこいつらの家か」イザクはあいかわらずの仏頂面で、 「だがどっちにも行くぜ。とくにその足音の話だ……この二人にまかせておいたら何をしでかすかわかったもんじゃないからな」 「ふむ」 デューラムは腕を組む。……確かになかなか、面白そうだ。一人で何日も苦しんでいた間は憂鬱でしかなかった現象だが、いざ仲間をえたとなると、がぜん待ちかまえているのは心踊る捕物帖であるように思えてくる。われながら単純だと思わないでもなかったが、気分というのは陰鬱であるより高揚していたほどがよっぽどいい。 よし、と呟くとデューラムはジョッキに残っていたエールを飲み干し、立ち上がる。 「そうと決まれば場所を移して計画を練ろうじゃないか。きちんと見張りと犯人確保の手段を考えておかないと、おまえらは次々と寝落ちするに決まってるからな!」 もう少し飲んでからに、とぐずるツァランをせき立て、一行は酒場を後にした。夜が深まりつつある時刻ではあったが、酒場を出てすぐの通りはいつもながらほどほどに猥雑で、酒場のすぐ横の潰れかけた雑貨屋の軒先では飲みほうけた三・四人の男達がぼんやりした目で座り込んでいた。 「しかし楽しみだな、男を睡眠不足にさせる幽霊たあ、また色っぽいからな――おっと!」 薄汚れた中型の野犬が何匹か、安食堂の裏の生ごみを漁っているのをうっかり蹴り飛ばしそうになりながら、ダグラスが言う。 「じっさいおれの部屋にご登場願いたいよ。生身でない女ってのはこう、手とか胸とかどんな風かな。やっぱり触ってもすうっと、こう、通り抜けちまうかな」 「知らないのか、そりゃあいろいろ具合が良いが、それが怖い。一度深入りして気がふれても知らんぞ」 ツァランがにやにや笑った。「まあ、それは冗談としてぼくも楽しみだ。なにやら面白そうな匂いがするからな。恋のロマンスの一幕であったとしても、胸を刺す悲劇の幕開けだったとしても、おどろおどろしい幽霊譚の始まりだったとしてもだ」 「上々だ。――ようし幽霊!」 ツァランの笑みを受け、デューラムもまた不敵に、そして無邪気に笑ってみせた。「おれを睡眠不足にした報いをしっかり受けるがいいんだ。いつでも来い!」 「いい心意気だぜ、そうこなくちゃ」 ダグラスの太い腕がデューラムの肩に回されてくる。「いつでも来い、打倒幽霊!」 こうして酔っぱらった彼らは、しぶるイザクを無理やりまじえてスクラムを組み、幽霊打倒、闘争勝利を連呼しながら二人の家までの道のりを練り歩いたのだった。 |