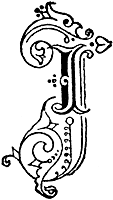 NVITATION TO THE UNDERWORLD.
NVITATION TO THE UNDERWORLD.
思わせぶりな発言をした後は、すぐに自分の世界に入り込んでしまったようで、その後エーリーンは何を話しかけてもろくな返事を返してよこさなかった。デューラムはあきらめて、黙々と道を歩いた。さっきまで晴れていた空はいつのまにか濁って、ちらちらと雪を落としだしていた。
やがて、すっかり日も暮れて一面青灰色になった視界のさきに、ぽつんとオレンジ色のあかりが見えてきた。イザクの小屋である。そのまま行くと、小さな小屋の、小さな屋根の、小さな煙突からもくもくと煙が出ているのも見えた。中に入って濡れた靴下を脱ぎ、暖炉の火に手をかざすことを思い浮かべて、デューラムは待ちきれない思いだった。
ところが、いざ小屋に近づき扉をノックすると返事がない。デューラムとエーリーンは顔を見合わせた。窓からは光がこうこうと漏れていて、不在のはずはない。
「イザク!」デューラムは叫んだ。「イザク!」
すると、小屋の横から大きな木のスコップを持ったイザクが顔を出した。
「何してるんだよ」
「雪を落としてた」
なるほどとデューラムは思う。三角屋根から雪が勢い良く落ちると、垂れ下がった長いつららが小屋の壁を傷つける。それで、スコップでつついて落としていたというわけだ。
「なんで今頃。昼間にやっておけばよかっただろ」
「ほかにすることがあった」
ぶっきらぼうに答えるイザクに、エーリーンが軽く手を振った。「あたしもおじゃまするわよ」
イザクはとくに答えを返すでもなく、ふんと鼻を鳴らすと、「中に入ってろ」と言い残し、小屋の裏に戻って行った。エーリーンがむくれる。
「よく来た、くらい言ったらどうなの。ろくに挨拶もしないで」
「いつものことだろ。あれがあいつの礼儀なんだよ」
ぶつぶつと文句を言っているエーリーンを、デューラムはなだめた。彼女はむっつりとして小屋の入り口の取っ手に手をかけたが、突如勢いよく振り返った。肩や頭に積もった雪を振り払いながら後に続こうとしていたデューラムは、その体にぶち当たりそうになって、あわてて足を止めた。
「ね、そうだわ!」と、エーリーンは満面に喜色を浮かべ、「さっきはまだ明るすぎて駄目だったけど、このくらい夜になってしまえば、今度こそ出てくるかも知れないわ。見たいでしょう?」
「何がだよ」
「三角小鬼よ!」エーリーンはにんまりと笑った。「この家と林のあいだにも、たしか格好の三角形があったわ」
たしかに小屋の裏には何本か木が生えていたはずだが、それぞれの位置関係などデューラムには思い出せなかった。彼は口ごもった。小鬼の話などはなから信じていなかったし、加えて体はすっかり冷えていたから、早く家の中に入りたかった。
「しかし、イザクがすぐ来るぜ。やつはそういうことには顔を突っ込まないよ」
「べつに二人で行けばいいじゃない。すぐそこよ、イザクが雪下ろしを終える前に帰って来られるわ」
「しかしなあ、おまえ」と、デューラムは疑わしげに、「仮に、小鬼が出るっていうその話がほんとだったとしても、だ。そんなちょうどいいタイミングで出てきてくれるわけがないだろ。一晩中じっと雪の中に立って木を見てるなんて、おれはいやだぜ」
するとエーリーンはつんと鼻先を上げた。「一晩中なんてあたしだってお断りだわ。小鬼の足跡が残ってるかどうか、ちょっと見て来るだけじゃない……。いいわよ、もう。あたし一人で行ってくるわ」
いかにも呆れた、という目で一瞥されて、デューラムはあっけにとられた。呆れるべき行動を取っているのはどちらだというのだろう? 歩き出したエーリーンをデューラムは仕方なく追いかけた。
「何よ、来るの?」
「行くよ、しょうがない」デューラムは半ばうんざりとしながら言った。「しかし小鬼の足跡とかってのが無かったら、今度一杯おごってもらうからな」
ちらつき加減だった雪は、しだいに激しさを増して、視界はかなり悪くなっている。イザクの小屋の裏に回ると、たしかに林の少し手前に、低めの木がちょうど三本立っているのがぼんやり見えた。ふだん人の歩かない雪原は、先ほどの小道よりもずっと歩きづらく、一足一足をひざで漕ぐように進めねばならない。
「おうい」とデューラムは言った。「こんな雪だったら足跡だって消えてるんじゃないのか」
だがエーリーンは振り向かない。深い雪の中を歩いているのは変わりないはずなのに、前を行くその足どりは奇妙にすべらかだ。デューラムは溜息をついて重い足を進める。
それにしても、とデューラムは思う。なぜ「小鬼」なのだろう? エーリーンの話によれば、地下世界は見渡すかぎりつづく花畑のなかを清流が流れる、それは美しい場所だというではないか。そうした場所に住む、花を愛する生き物を、「鬼」という名で呼ぶのがデューラムにはしっくり来なかった。花の精とか精霊とか、いくらでもふさわしい呼び方がありそうなものではないか……
雪はやみそうになかった。ゆくての林は木々の枝を空高くそびえさせ、闇夜のなかのさらに濃い闇となって佇んでいる。雪の粒は音もなく、次から次へと地面に降り積もってゆく。風はない。あたりは沈黙に包まれており、そしてその沈黙は鼓膜をしんしんと軋ませるのだった。ただ口元に白くわだかまる自分自身の息の音だけが、やけにはっきりと意識される。まっしろな無音に目の奥が痛んだ。
「エーリーン」デューラムはもう一度叫んだ。「戻ろうぜ。雪がひどい」
と、今度ばかりはエーリーンも立ち止まった。デューラムはほっとして、彼女に近づこうとしたのだが――そのとき、そのエーリーンのさらに前方にあるものを見てはっと息を飲んだのだった。
それはデューラムとエーリーンが立つ場所から、距離にして数十歩の場所だった。くだんの三本の木の、ちょうど真ん中である。そこで地面がうっすらと、銀色に光っているのだ。
目をこらして見ないとわからない、ごくわずかな光ではあった。けれども確かに雪の層をとおして、何かしらのかがやきがぼんやりと透けて見えるのだ。間断なく落ちてくる雪の粒がその淡い光に下から照らし出され、まるで無数の銀砂が木々のあいだを舞い散るかのごとき光景だ。思わずデューラムはその場に立ち止まっていた。
「ああ、見て!」前方のエーリーンがすべるように体をすりよせてきて、ささやいた。「三角小鬼がやって来ようとしているわ!」
そんな馬鹿な。
デューラムはそう言おうとした。けれども雪の下に輝く光を、まぎれもなく今、彼も目にしているではないか。言葉を失っているデューラムの袖をエーリーンが興奮したようにぎゅっと掴む。「ごらんなさい、あの光の上――扉が開くのだわ!」
そう、エーリーンの言うように――輝く雪の地面の、その上の空間に、何かえたいの知れないひずみのようなものが生じつつあるのが見えた。いちめん青灰色の雪の夜の中で、はっきりとした何を確認できたわけでもない。しかし、たしかに何かがねじれているのだ――まちがいなく、その場所で。そしてそのひずみの中に少しずつ、ひとつの光景が浮かび上がっていくのだった。
「扉」とエーリーンは言った。が、なにかしら雪の地面が、空間が、口をぽかりと開けたわけではない。そうしたものをデューラムは認識しなかった。ただ光の上に浮かんだ軋みのなかに、あるいは軋みを通して、あるいは軋みのまわりに――そうとしか形容できぬ知覚だったのだが――色とりどりの花が乱れ咲く豊かな丘を、彼は見たのである。どこまでも続く丘のまにまに小川が流れ、木々は白や桃色や黄色の花をあふれんばかりにその腕に抱えている。藍と灰色の濃淡に占められ色彩の欠如した真冬の世界の真ん中に、ただそこにだけ、あたたかな春の光景が果てしなく広がっているのだった。
その花畑のなかを、ときおり赤茶色の何かが飛び跳ねている。二匹、三匹……。長い毛に覆われた……狐か? 犬か? 否! あれは手と足をもつ何かだ。まるで猿のような……。だがよく見えない。ずいぶん素早く、まるでばったのように跳び回るし、何より遠いのだ。遠くてよく見えない……。
「もうすこしなら大丈夫のはずよ」と耳元でエーリーンがささやく。「三角小鬼はあの木の三角形から出ては来られないのだから。もう少しなら、もう少しなら、近づいても……」
デューラムは重たい雪を漕いで、よろよろと足を進めた。どこかで誰かが自分の名を呼んだ気がした。けれども眼前の光景も、エーリーンのささやき声も、冷気にかじかんで感覚を失った自分の手足の動きも、もとよりすべてはまぼろしのようで、どれが信頼に値する知覚かもわからなかった。ぎゅっと強くまばたきをすると、まつげにまとわりついていた細かな雪のつぶが溶けて頬を流れ落ちてゆく。ああ、とデューラムは思う。あの赤茶色の生き物が長細い手を伸ばしている。こちらに来ようとしているのだ。節くれだった手が雪の地面を掻く……長く尖ったかぎ爪を生やした鬼の手が……。
そのとき突然、野太い声が鼓膜に響いて、デューラムははっとした。
「デューラム!」
思わず振り返ろうとしたデューラムは、後ろから迫ってきた影に勢いよくぶつかられ、そのまま前倒しに雪の上に倒れた。粉雪がぱっとあたりに舞い散った。
「デューラム!」勢いにまかせて一緒に倒れた影が、まぢかでもう一度怒鳴った。「このうすのろめ、目はどこについてやがる!」
「イザク」デューラムはあっけにとられた。「突然何をするんだよ!」
「そりゃこっちの台詞だ。何度も呼んだのに気づきもしねえ」
雪まみれになったイザクは、四つんばいのまま大きな目でデューラムをにらみつけた。「あっちに古井戸があるのを忘れたわけじゃないだろうが。今は雪に隠れてて危ないんだ。ふらふら前後不覚に歩いて行きやがって、落っこったらただじゃすまねえぞ」
「古井戸?」
おうむがえしに言ったデューラムは、上半身を起こして周囲を見た。雪は変わりなくしんしんと降り続いている。いっぽうにはイザクの家のあかりがぽつんと橙色にともっている。反対側の、林のそばには木が何本か立っていて――だが、それだけだった。
デューラムは混乱した。先ほどまで確かに見えていた銀の光は、異界の花畑はどこへ言ったというのだろう? あの赤茶色の影は? いや、それより、
エーリーンは?
「まずいぞ」と言ってデューラムは慌ただしく立ち上がった。「そうだ、古井戸があるんだったな? エーリーンはそれを知らないんだ。早く止めないと危ない――」
「おい待て」
林のほうに向かおうとしたデューラムの腕を、後ろからイザクが掴む。「危ないのはおまえだ。少し落ち着け、誰がどうしたって?」
「だから、エーリーンがいないだろ。きっと林の方に歩いて行って……」
「エーリーン?」
デューラムは振り返った。「おれと来ていたじゃないか。二人で一緒に裏に回ったんだ」
イザクはとほうに暮れたような顔でデューラムを見返してきた。「おまえは一人で来ただろ」
デューラムはあんぐりと口を開けた。「馬鹿を言うなよ。はっきりおぼえてる。小屋の戸口の前で、おまえもあいつに挨拶を返したじゃないか」
「おれはエーリーンなんぞ見てない。おまえが来たから、中に入ってろと言った。それだけだ。ところが小屋に戻ってみれば、中には誰もいないし、おまえは小屋の裏で一人で雪に埋もれてた」
デューラムは愕然とした。
――あたしもお邪魔するわよ。
――失礼だわ、ろくに挨拶もしないで――
そう、彼女はたしかにイザクに声をかけていた。そしてイザクはデューラムらのほうをちらりと見て、『中に入っていろ』とだけ言って、去って行ったのだ。あのとき、てっきりデューラムは、あれがエーリーンの挨拶に対するイザクの反応だと思ったのだ。イザクは度を超した無口で、ふだんから、声をかけてもろくに返事もしてこないくらいだったから……。
だが、もしエーリーンがあそこにいなかったとしたら?
それでも、記憶にあるイザクの反応に、なんら不自然な点はないではないか。
しかし、しかし、では先ほどまで連れ立って歩いていたはずの、彼がエーリーンと信じて疑わなかった「あれ」は、いったいなんだというのか。たしかに雪原のまんなかに立ち尽くしていたり、雪の夜に鬼を見に行こうと誘ってくるなど、ふつうの人間の行いではない。だが、エーリーンは普段からそういう行動が目立ったから、デューラムとてとくに気にせずに……。しかし……。
そうだ――そうだ! 思い出せ。エーリーンを見つけたあのとき、彼女はどこに立っていた? 三本の木が三角に立ち並んだ、まさにその真ん中だったではないか……。そうして、デューラムが道を離れ、彼女の方角に足を踏み出したとき、その先はまっさらな雪だったはず。誰の足跡もない……。
では、あのときエーリーンはどこからやってきたというのか。
――三角小鬼はね、冬に出る鬼なの。三本の木がきれいな正三角形を描いてる場所は、小鬼たちの国につながっているのよ。
――とくに、真っ白な雪がふかふかのじゅうたんになってて、人の足跡のないところはね。
デューラムはぐらりと視界が揺らぐのを感じた。
「頼むから、もう少しだけ饒舌になってくれ、イザク」と、彼はうめいた。「さもなくばおれの生死にかかわりかねないんだ」
しかし、イザクはふんと不機嫌そうに鼻を鳴らしただけだった。

それから数日経って都に出たデューラムは、酒場でエーリーンにつかまって、さんざんなじられるはめになった。
「なによその目。まるで鬼か幽霊でも見るみたいな顔して」とエーリーンはこれ以上もなくつんつんした態度で、「……とにかく、とんだ濡れ衣だわ。あんた、雪のなかであたしに化かされて井戸に落とされそうになったなんて言いまわってるそうね。イザクに聞いたわよ」
もののけにこちらが化かされるほど無口で無愛想なくせに、こういうことだけきっちりと本人に伝えているのかと、デューラムは暗澹とした思いでため息をついた。エーリーンの愚痴はほうっておくと何日でも続きそうだったので、デューラムは隙をうかがって質問してみた。
「なあ、三角小鬼って知ってるか」
「なによ、話をずらそうとして」とエーリーンはデューラムをにらみつけ、「たしか、木が三角に生えてるところに出てくる雪鬼じゃなかったこと。知り合いの姿で人を化かすって言うけど……。なあに、もしかしてあんた、このあたしをそれと間違えたっての?」