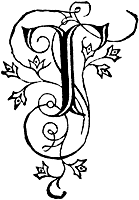 REES IN TRIANGLE.
REES IN TRIANGLE.
澄み渡った雲に浮かんだ雲が西日を受けてうっすらと桃色に染まっていく。昼間はいちめん真っ白に輝いていた雪のじゅうたんも、空のかげりとともに少しずつ青みを帯びてくる。なだらかな丘陵の谷間には夕闇の陰翳が沈殿していた。丘陵を走る小道を歩いていたデューラムが、道の横に人の影を認めて立ち止まったのは、そんな夕暮れだった。
小道から少し離れた場所である。大人と同じくらいの背丈の、若木が二、三本立ち並んだ、その中にまぎれるように立っている。周囲の若木も雪の衣を厚くかむっていて、一見すると人かと思うようなシルエットだ。しかし今デューラムが見つめているものは、それらの木々とはたしかに違うものだった。人だった。
外套のフードをかぶった小柄な影である。
――何だ?
デューラムは眉を寄せた。ここはカリャンスクの村から林に向かう小道である。道の先には何軒か家がある。この道を通って薪を集めに行く村人もいる。だから、すれ違う人間がいてもおかしくはない。だが、その人影は奇妙だった。なぜこんな夕暮れに、こんな何もない場所で、しかも道から離れたあんなところに立っている?
何をするでもない。人影はこちらに背を向けて、両手両脚をそろえて若木の前に突っ立っているだけである。
何か異様なものではないのかと、はっきり思ったわけではない。ただ不安がわずかに燻った、その次の瞬間に、びょうと風が吹いた。頬を切る冷気に身をすくめたデューラムは、同時に、小さな影のてっぺんからふわりと横に流れる赤い色を見た。きゃしゃな手がすっと伸びて、その赤毛をおさえた。
「エーリーン!」
呆れ声で、デューラムは叫んだ。小さな影が振り返る。デューラムはまっさらな新雪にずぼずぼと長靴を埋もれさせながら、道を離れ、早足でその影の方へと向かった。
外套のフードをかぶっていたからわからなかったが、まぎれもなく彼の飲み仲間の一人、エーリーンである。つかみどころのない、ふらふらした女だ。ふだんは都の酒場で竪琴を弾いたりしているが、たまにカリャンスクの飲み屋にやってくることもある。
若木が三本集まって立った、その真ん中に立っていたエーリーンは、デューラムに向かって手を振った。
「何してんだよ、こんなところで。凍えるぞ」
デューラムは手を差し伸べて、ひざのあたりまで雪に埋もれているエーリーンを道のほうに引っ張り出した。彼女はくすくす笑った。
「木を見てたの」
「木を? こんな夕暮れにか? どのくらいああしていたんだよ」
「ほんのちょっとの間よ。……だって夜は怖いじゃない」
昼間にしろよ、とデューラムは思うが、おそらく言っても無駄なので、溜息をつくにとどめておいた。「しかし、もう今日は街には帰れないぞ。<赤ぎつね>に泊まるのかよ」
エーリーンがたまに竪琴を弾く村の酒場の名前を言うと、彼女は首をかしげた。「そうねえ。あんた、どうするの」
「うちはだめだ」と、デューラムは先手を切ってやった。「おれはこれからイザクに貸してた斧をとりにいって、そのまま、やつの家に泊まってくるからな。ほら、まだ一人で村に帰れるだろ。気をつけて行けよ」
言うなり、デューラムは歩き出す。多少つっけんどんにしておかないと、この女は要求しだせばきりがない。
すると、エーリーンは「あら待ってよ」と言って、慌てたように追いかけてきた。「あたしも泊まってくから、一緒に行かせてよ」
「おまえなあ」とデューラムは呆れて振り返り、「イザクのこと苦手なんじゃなかったのか。あんな無愛想はしゃべっててちっとも面白くないだの、なんだの、悪口ばっかり言って」
「苦手だけど、でも友だちだし、たまには三人もいいじゃない。それに……」と、ポケットから毛のミトンを取り出したエーリーンは、そこで言葉を切って、デューラムの顔を覗きこんだ。「あんただって、夕暮れにひとりで歩くの、怖いでしょ」
「おれは怖かない」
「それにしちゃ、さっきはずいぶん神妙な顔して近づいてきたじゃないこと」
「気づいてたのかよ」とデューラムがにらみつけると、エーリーンはまたくすくす笑った。
「へんな場所に人が立ってると、そう思ったのでしょ」
「思ってない」
「うそばっかり」
「少しだまれよ、おまえは。こんなに寒くちゃ口を動かすのもおっくうなんだ」
言ってやると、エーリーンはつまらなそうに、ふうんと鼻を鳴らした。
しばらくの間、ぐっ、ぐっ、と二人が雪を踏みしめる音だけが続いた。すでに何人かが踏み固めた道だが、それでも雪はまだやわらかく、一歩足を進めるたびに長靴がくるぶしのあたりまで沈む。難儀な冬の道だったが、イザクの家もそろそろ近いし、何よりもう暗い。多少急いでもよいと、デューラムは足を速めた。
木こりのイザクは、カリャンスクの村と林の境界あたりの小さな木の小屋に一人で住んでいる。真冬には寒くてたまらなそうに思える粗末な小屋だが、どうしてなかなか、暖炉を囲めばそれなりに暖かい。デューラムの家からは歩くと少し時間がかかるのだが、その付近に漂う林の匂いに惹かれて、彼はたびたび遊びに行く。イザクの小屋では、夜に風が吹くと背後の林が頭上高くざあざあと音を立てる。それがまるで遠くに流れる川のせせらぎのようで、なんともいえない空気の深みを感じさせるのだった。
ああいう人のすみかと森の境界っておっかないのよ、などとエーリーンは常日頃言っている。人みたいで人じゃないものが、木のあいだから覗いてくるのがたまに見えたりしちゃうんだから。そしてそういうところに住んでると、人だったものがいつのまにか人でなくなったりしちゃうんだから……
まあ、イザクみたいな強面だと、そんな面白いことにはならなそうだけど、とエーリーンはどこまでも失礼である。しかも、それを本人の前で言うのだ。デューラムら男衆の気が利かなくて無礼だなどと文句をつけるわりに、彼女じしんが人を人とも思わぬ口をきく。それでも不思議と、本気で腹が立つことは少ない。エーリーンの話は突拍子がなく、根拠のない決めつけ以外の何ものでもないのに、どこか奇妙な真実味がある。
――イザクみたいな仏頂面だったら、鬼だの妖精だののほうが逃げちまうわね。だからあそこに住んでても平気なんだわ。
エーリーンが以前に言っていた台詞をデューラムは思い出す。
――だけど、デューラム、あんたみたいに騙されやすい人は駄目。すぐにあっちに引きずりこまれちゃうんだから。気をつけた方がいいんだわ……
「だけど、あのあたりが怖いってのも」
とつぜんすぐ後ろで当の本人がしゃべったので、デューラムはぎょっとした。
「なんだって?」
「そんなに驚かないでよ」とエーリーンは不機嫌そうに、「あのあたりが怖いってのも、まんざら勘のきかない話じゃないわねって言ったの。あそこに生えてる木、三角だったでしょ? それが遠くから見えたもんで、あたしは気になって見に行ったんだわ」
「あそこ?」
「あそこよ、さっきあたしたちが会ったところ。三本の木が三角形に生えてたでしょ。気づかなかった?」
言われてみれば、三角形だったような気もする。
「記憶力が悪いのねえ!」
馬鹿にしたような、呆れたようなエーリーンの口調にデューラムは口をとがらせた。「木の生え方なんていちいち覚えていられないよ」
「そんなんだから、いっつも変なものに化かされるのよ」とエーリーンは手きびしい。「気をつけるってことをまるで知らないんだから」
このような不条理な罵倒には慣れっこだったので、デューラムは「はあ」と適当に唸っておいた。「それで、木が三角形に生えてると何が起こるって?」
すると、エーリーンはしいっと大げさな動作で唇に指を当てた。それから、デューラムの耳にミトンの手を寄せると、わざとらしく声をひそめ、「三角小鬼が出るのよ」と言った。
「三角小鬼?」
「そう」と、エーリーンはくるりと振り向いて、後ろの方を眺めやるように手をかかげた。「知ってて? 三角小鬼はね、冬に出る鬼なの。三本の木がきれいな正三角形を描いてる場所は、小鬼たちの国につながっているのよ。とくに、真っ白な雪がふかふかのじゅうたんになってて、人の足跡のないところはね。月夜の晩になると、そういう三角形から小鬼がやってくるのよ」
「ふうん」とデューラムは唸った。聞いたことのない話である。もっとも、鬼だの妖精だのの話は何度聞いてもすぐに忘れてしまう彼ではあったのだが。
「だけど、前にキノコの生えた円の話をしていただろ。あれも妖精の国につながっているんだろ? それとは違うのかよ」
「違うわね。地下にはいくつもの世界があるのよ。そしてそれぞれの地下世界への扉のありかは、みんな違ってて、みんなちゃんとルールがあるの」
腑に落ちない様子のデューラムを、エーリーンは横目でちらりと見ると、ふと歩きながら腰をかがめて足下から雪をすくった。「見て」と言って手を突き出してくる。
「なんだよ」
「雪のお花。綺麗よねえ」
見れば、エーリーンの毛糸のミトンの上で、雪の小さな欠片がきらりきらりと光っている。昼すぎまで降っていた雪が、まだきれいな星型を残して積もっているのだ。目を凝らさないとわからないほど微細で、薄い欠片なのに、どれも美しく均等の取れた複雑な六角形を成している。いかなる不思議がこんな技を成しとげるものかと、デューラムもいつも怪しんでいたものだった。
「その三角小鬼たちはお花が大好きで、そいつらが住んでる地下の国も、どこもかしこもお花だらけなのよ。かわいらしい小川や滝が緑のあいだを流れてて……。地底は死者の世界だなんて言うけれど、地獄の大鍋が煮え立って、みにくい竜が牙をむいてるようなとこばかしじゃないのよ。そして、正三角形に立ち並んだ若木の真ん中は、常春の小鬼の国に続いているんだわ……。
でも、この世のあらゆるお花が咲き乱れた、そんなきれいな小鬼の国でも、ひとつだけないお花があるの。三角小鬼の国は地下にあるから、雪が降らないの……。だから、自分たちの国で見つからないたった一つの花を手に入れるために、小鬼は雪が降ると三角の若木の扉を抜けて、こちらの世界にやってくるのだわ。そして新雪のじゅうたんを思う存分踏みしめて、雪の花を思う存分すくって遊ぶのよ」
「ふうん」とデューラムは少し感心しながら、半ばはからかい半分に、「それじゃ、おまえはその鬼をつかまえようと思ってあそこにいたってわけか」
「そうよ。でもやっぱり、少し時間が早かったみたい。三角小鬼は夜にしか出ないのよ。だからあたしは夕方を狙ってみたんだけど……」
だめだったわあ、とエーリーンは溜息をついた。「かわりにあんたが出てきたもんで、日常に引き戻されちゃった」
「見飽きた顔で悪かったな」とデューラムはぶうたれた。「そんなこと言うけど、見たことないんだろ。その三角小鬼」
「あら、あるわよ」
「うそつけ」
「うそじゃないわ。ほんとよ」
いつになく真剣な声でエーリーンがそう言ったので、デューラムはまじまじと彼女の横顔を見た。
「どんなふうな姿をしてたか、知りたい?」
言って、エーリーンは溶けかけた雪の星をふっと吹き飛ばした。すっかり暗くなった空の下で、雪のかけらは一瞬だけきらりと光って消えていった。
「でも、教えてあげないわ。あんたがそりゃあ驚くような姿をしていたって、それだけ」