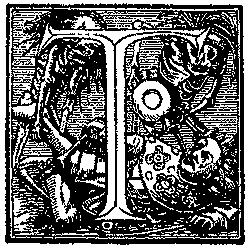 IEVES' LIGHT.
IEVES' LIGHT.
ヒルダの家は《ロバートの道具店》前の通りを終わりまで下って、それから少し歩いた場所にあった。三階建ての建物の一階が彼女の家で、上には別の家族が住んでいるという。夫婦ふたりが暮らしていた家はこじんまりとして狭く、戸口を入ってすぐの居間には、どこかじめっとした空気が漂っていた。
エーリーンはいつにも増して落ち着きのない様子で、暖炉をじろじろ眺めたり、窓枠を触ってみたり、かと思えば隣の寝室を勝手にのぞきこんだりしている。人数分のマグと水を用意してきたヒルダが、不可解そうに、ちらちらとその様子をうかがっていた。
たといややこしい事態と言えども、亡くしたばかりの夫とふたりで使っていた寝室に、見知らぬ他人に土足で踏み込まれるのは気分のいいものではあるまい。エーリーンのふるまいは無遠慮にすぎるような気がして、アルマはたしなめるように、「エーリーン」と名を呼んだ。
するとエーリーンは振り返って、こちらに戻って来たかと思うと、水の入ったマグを見て眉を寄せた。
「ミルクがほしいんだけど」
「ミルク?」
「そうよ。ないの?」
ヒルダは戸惑ったように、「あいにく、今切らしてて……ごめんなさい」
「じゃあ、もらってきて」
高飛車な物言いである。アルマは語調を強め、もう一度「エーリーン」とたしなめた。
だが、エーリーンはアルマを無視した。「早くしないと、深夜になっちゃうわ。上の人か隣の人か、誰かくれるでしょう?」
アルマは溜息をついて立ち上がった。「わたしが行きます、ヒルダ」
アルマのノックに応えて、扉から顔を覗かせた上の階の住人は、三十代半ばの太った女だった。ミルクをわけてくれという見知らぬ人間の申し出に、女は少なからず面食らったようだったが、アルマがヒルダの名前を出すと、ずいぶん不信感が薄れたようだった。ちょっと待っていろと言って奥に引っ込んだ女は、しばらくして半分ほどミルクで満たされた水差しをこちらに渡してよこした。女のスカートの影からは、まだ年端もいかない子どもがおっかなびっくりこちらをうかがっていた。
ミルクを持ってヒルダの家に戻ると、ヒルダとエーリーンが何やら寝室でごそごそやっているところだった。見れば、二人は衣類やら毛布やらを引っ張り出して寝台の中に押し込んでいるのである。
「何してるの」
エーリーンはアルマの声に振り返ると、質問にもろくに答えず、「ああよかった」と言って、水差しを受け取った。マグにミルクを少しついで、一口飲む。ただエーリーンがミルクを飲みたいがために、自分は見ず知らずの奥さんにミルクをもらいに行かされたのだろうかと、アルマはあきれた。
「いい、さっき言ったわね、ヒルダ」と、ミルクの水差しを横に置いたエーリーンは、いつになく険しい表情で言い放った。「今晩はベッドで寝ないのよ。かわりに囮(おとり)を入れたわ。あたしたちが入るのは、あそこ」
どうやら、エーリーンとヒルダが寝台に詰め込んでいたのは「囮」であるらしい。エーリーンが指差した方向を見れば、衣装棚がある。ぎゅうぎゅうに詰めれば二・三人が入れないことは無いかもしれないが、どう見ても足をゆったり伸ばせるスペースはない。
「何があっても、絶対に声を出しちゃだめよ。身動きもしちゃだめ」
有無を言わせぬ口調でそう言い放つと、エーリーンは鋭い目で窓の外をちらりと見た。
そして、「そろそろね」と言った。
居間と寝室の灯りを消すと、あたりは真っ暗になった。家具をひっくり返さないよう、そろりそろりと足を動かして、アルマとヒルダは指示された衣装棚に入り込んだ。衣服を隅に押し寄せ、しゃがみこむように並んで縮こまる。衣装棚の中は古着と毛織物の独特の匂いが立ちこめていて、あまり良い空気ではなかった。
二人の後からエーリーンが入り込んでくる。細い体の彼女とはいえど、さすがに三人の体重を乗せると棚の底板もおぼつかなくなるようで、たえずぎしぎしと軋み音を立てては、いまにも底が抜けるのではないかとアルマを不安にさせた。「物音を立てるな」とエーリーンは言ったが——そんなことが可能なのか? いや、今は音を立ててもまだ大丈夫なのだろう。問題は、
——来るかもしれないわね。
先ほどのエーリーンの言葉が頭に浮かぶ。
しかし、いったい何が「来る」というのか。パーベルは死んだと、当のヒルダがはっきり言った。彼の死体は、衛兵が運んで行ったのだと。その死体が夜中に起き上がって、ここまでやってくるというのだろうか。あるいは、パーベルのたましいが……幽霊というのだろうか? それが、ここに出没すると?
——ヒルダを連れてゆくために。
わからない。エーリーンはただ、「彼が」来るかもしれないと言った。それ以上の説明は、なにもなかった。
時刻はもう真夜中を大分すぎていた。ヒルダは奥で壁に背をもたせかけるようにして、うつむいている。衣装棚の両開きの戸は細く開いていて、しゃがみこんだヒルダとアルマのあいだに立ったエーリーンが、じいっとその間から外を見つめていた。窓際にかかっている安物のカーテンは、あまり光を遮らないようで、部屋の中に青くらい光が差し込んでいる。下から見上げたエーリーンの顔を、その光が細く細く縦に照らしていた。いつもは緑がかった灰色であるエーリーンの瞳が、その光の中で銀色に光って見える。アルマは少しどきりとした。目をそらし、自分も同じように戸の隙間から部屋の中をのぞく。——と、
ちらりと、
——何?
「しっ」
思わず身動きしたアルマが床板を軋ませたのに、エーリーンが押し殺した警句を発する。ごめんなさいとアルマは口の中で呟いて——だが、今見たものを確認するために、もう一度目をこらした。
窓だ。
カーテンの向こうに、何か——
もう一度、すっと《それ》が窓の外を横切った。
アルマは息を飲んで、家の外をただよう小さな光を見つめた。人間の胸くらいの高さだろうか。右から左に、あるいは左から右に、闇の中をかぼそい光がひとつ、行き来しているのだ。
「来たわ」
エーリーンがささやいた。衣装棚の隅で、ヒルダが息を飲むのがわかった。
アルマは唾を飲み込んだ。押し殺そうとした自分の喉の音が、やけに大きく響く。
小さな光はゆらゆらと上下に揺れながら、窓の外を行ったり来たりしている。はっきりとは見えない。だが、サイズが合わなくてぴっちりと閉じないカーテンの両布のすきまから、ちらり、ちらりと橙色の光が覗くのだ。まるで誰かが蝋燭のかぼそい灯りをたよりに家の回りを動き回っているかのような光景だった。
ふと、光がカーテンのすきまの位置で止まった。
そのまま、じっと動かない。
まるで部屋の中を、そしてこの衣装棚の中を、
——見ているような。
背筋からうなじにかけて冷たいものが走り抜けるのを感じ、アルマはとっさに衣装棚の戸の隙間から身を引いた。がたんと床板が鳴る。
「アルマ!」
再度エーリーンの押し殺した叱責が飛んだ。心臓が喉から口の中に飛び出してきそうなほどに脈打っている。見えるわけがないと、頭ではわかっている。あちらは薄ぼんやりとはしているが、夜の光が照らす中にいる。他方、こちらは真っ暗な部屋の中の、さらに奥の衣装棚のごくごくわずかな隙間から外を覗いているに過ぎないのだ。外にいる誰かに、自分たちが見えるわけがない。それでも確かにアルマの体は、そのときはっきりとした視線を感じたのだった。
ぎいとどこかで音がした。ゆっくりとした軋み音——居間である。誰かが入り口の扉を開けたのだ。アルマは座り込んだ自分の頭のすぐ横にあるエーリーンの手が、ぎゅっと握りしめられるのを見た。ヒルダが小さなかぼそい声で、「いや」と呟く。泣き声だった。彼女は唇をかみしめて、いまにも漏れ出そうとする悲鳴を抑えているようだった。
扉の軋み音に続いて、足音が家の中に入ってきた。ごとん、ごとんと靴が木の床を打つ音。入ってきた何者かは、居間の中を歩き回り、あちこちをのぞきこんでいるようだった。アルマはもう一度、勇気をふりしぼって、衣装棚の扉の隙間に目を当てた。その直後だった。
《それ》がすうっと寝室の中に入ってきた。
開け放したままの扉から、足音とともに現れたのは、宙に浮かぶ小さな蝋燭の光だった。
アルマはこぼれそうになる声を押し殺すために口に手を当てる。
持ち主の姿は、見えなかった。
否、そう言い切っては嘘になったかもしれない。部屋の中はただでさえ薄暗く、闇に慣れた目であっても、何かの姿をはっきりととらえることはできなかったからだ。ベッドも、壁際の机も、何もかも、濃い闇の塊としてぼんやりととらえうるだけだった。その姿が「見えない」のが、はたして何か摩訶不思議な力によるものか、あるいは単に室内の夜の暗さのためなのか、アルマは確信を持てなかった。ただ彼女が見たのは、闇の中をぽつんと小さな光がひとつ、ゆるやかに上下しながら移動している、そのさまである。普通の蝋燭よりずっと小さなその光は、あたりをろくに照らし出しもしなかった。ただその光の周囲に、なにかぼんやりとした影のようなものが、わだかまりつつ移動している——そんな「気がした」。
ごとん、ごとんと足音がして、光は寝台のほうへ向かっていった。粗末な寝台は、人が毛布にくるまって横たわっているような盛り上がりを見せている。光は、寝台のそばの小さな机の上で止まった——まるで、誰かがそこに蝋燭を置いたかのように。
「神様」と、かすかな、声にもならない息でヒルダが呟いた。「神様、神様、神様」
次の瞬間、材木を力まかせに引き裂くようなひどい音を立てて、寝台の盛り上がりがつぶれ、アルマはあやうく飛び上がりそうになった。二度。三度。引き裂かれた毛布や枕のわたが、窓から差し込む青い光の中に舞い上がる。四度、五度。めきめきといやな音を立てて、寝台全体がひしゃげていく。
誰かが斧のような重たい武器で、寝台をめった打ちにしているのだ。アルマはぞっとした。本来ならば、あそこで横たわっているのはヒルダだった。
激しい音のさなかに、すぐ隣でヒルダが息を殺して泣いている息づかいを感じる。彼女が口の中で呟いているのが聞こえる。
「うそ、うそ。パーベル、うそよ。うそ。パーベル——ごめんなさい、ごめんなさい、許して、パーベル。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい、パーベル、許して、あたしを許して、許して、許して、許して、許して」
エーリーンがおそろしい表情でぐいと顔を寄せてくると、アルマの耳にぴったりと唇を寄せてささやいた。「その人をだまらせて!」
激しい音はまだ続いている。いまや寝台そのものが刃物でめちゃくちゃに打たれて、まっぷたつになろうとしていた。アルマは震える腕をそろそろとヒルダの体に回し、抱きしめて、その口を手でおさえた。ヒルダがぎゅっと目をつむるのがわかった。涙がぽたぽたと手に伝わる。
しばらくして音は止んだ。誰かの低く荒い息づかいが部屋の中に響き渡るのを、アルマは聞いた気がした。だがそれが自分のものでないという確信も、彼女には持てなかった。全身にびっしりと鳥肌が立っている。アルマはヒルダの口を抑えた片手の腕に自分の口を押し付けた。そうでもしなければ、次の瞬間に恐怖の叫びが喉の奥から飛び出しそうだった。だが少しでも声を出そうものなら、三人もろとも、目の前でぼろくずになっていった、あの毛布や枕と同じ命運をたどるのは目に見えていた。
見えない何かが、机の上の光をもう一度取り上げた。それから蝋燭の光は、ごとん、ごとんと足音を立てながら寝室の扉のほうへと進んでいく。お願いだからそのまま立ち去ってくれと、アルマは切に願った。もう恐怖は限界で、あと少しで彼女もわめき出してしまいそうだった。 蝋燭の光はゆっくりと衣装棚に近づいてきて、その前を通り過ぎようとして——
動きを止めた。
アルマは暗闇の中、目を見開き、痛いほどに唇を噛み締めた。総毛立つ感触がざあっと全身を上ってくる。
横に立つエーリーンの体が緊張するのをアルマは感じ取った。彼女はそろそろと、音を立てぬよう細心の注意を払いながら、腰をかがめ、守るように足下に置いていた《何か》に手を伸ばした。アルマはそれが何なのか頭の片隅でいぶかしんだが、恐怖のためにわけがわからなくなっていて、深く考える余裕もなかった。
抱きしめたヒルダの体が震えている。
外の光がすうと持ち上がる。逡巡するようにまたたいてから、棚戸の隙間から中を——
その刹那、エーリーンがこれまで聞いたこともない金切り声をあげたかと思うと、一気に棚から外に飛び出した。同時に、何か液体のようなものが部屋の中に飛び散る気配と音がしたかと思うと、まるで獣の咆哮のような悲鳴が部屋の中に響き渡った。
ふっと蝋燭の光が消え失せた。
ついで、何か動物のような、あるいは四つんばいになった人間のようなもののシルエットが、低い唸り声をあげながら目にも止まらぬ早さで床を這いずり、寝室を飛び出して行った。その影はさらに居間を駆け抜け、開け放しになっていた家の扉から、夜の中にそのまま走り去って行く。
後には静寂だけが残された。
エーリーンが大きく肩で息をしながら、部屋の真ん中に座り込んでいる。
アルマは大きな息をついて、ヒルダに回していた腕をゆっくりと放した。ヒルダは放心したように、衣装棚の後ろの壁にもたれかかった。
「パーベル」と、ヒルダはすすり泣いた。「ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい」
アルマはその様子を見ているのが痛ましくて、エーリーンに目を戻した。
「行ったの」
アルマが聞くと、エーリーンがのろのろとこちらに顔を向けて、頷いた。
部屋の中には独特の匂いが立ちこめている。アルマは先ほど飛び散った液体の飛沫が腕にかかっていたのを指ですくって、舐めてみた。やはりミルクである。
「ミルクをぶつけたの」
「そう」
エーリーンは脱力したように頷いて、「《盗人たちの灯》は、水じゃ消えないの。ミルクでなけりゃ」
そう言うと、彼女は気だるそうに立ち上がった。「昔、ある家に《灯》を持ったどろぼうが入ったとき、その家の女中が撃退したって言ったでしょ。彼女が最後に《灯》にぶつけて、ようやく炎を消すことができたのが、ミルクだったんですって」
このときになって、アルマはようやく、先ほどなぜ自分がミルクを取りに行かされたのかを理解した。あれは別に、エーリーンがミルクを飲みたかったからでも、なんでもなかったのだ。あれは、《盗人たちの灯》をもつ者に、彼女が対抗するための道具だったのだ。
エーリーンはランプに火をつけると、腰をかがめ、床にできたミルクの水たまりから何かを拾い上げた。「ごらんなさい」と言って、ランプの灯りにかざして見せる。親指の半分ほどの長さもない、ごくごく小さな棒状の何かだ。アルマは近づいて目を凝らした。
それは、たった一本の、小さな小さな赤ん坊の指だった。

ほどなくして朝が来た。ヒルダは深く心を痛めている様子だったが、アルマとエーリーンには目に涙を浮かべて何度も礼を言った。あまり深く考えすぎるんじゃないのよ、とエーリーンは言った。終わったことだし、仕方なかったんですよ、とアルマも言った。ヒルダはうつむいていた。
それから一月ほどが何ごともなく過ぎた。アルマは何度かヒルダを訪ねて行ったが、彼女は表情に若干の影があったものの、ふつうに生活を送っているように見えた。が、そのうちにヒルダがいなくなったという噂を聞いてアルマは胸騒ぎを覚えた。働き者の彼女は、夫がいなくなっても変わりなく仕事に出て気丈にふるまっていたのだが、ある時めずらしく、三日つづけて姿が見えなかったのだという。心配した仕事仲間が彼女の家に行ってみると、まるで普通に誰かが生活していたような状態のまま、ヒルダの姿だけがなくなっていた。食料も、なけなしの金も、衣服も、みんなそのままなのだった。机の上には、小さな髪飾りや、きれいな石や、安物だが可愛らしい皿などが点々と並んでいた。昔、ヒルダが嬉しそうに、夫からのプレゼントだと言って使っていたものばかりだった。
しばらく経って、ヘプタルクの市壁の外を流れる大きな川の河畔に、女の死体が流れついたという噂が流れた。川が深くなっている場所で、橋から身を投げたようだということである。死後何日か経っていたようで、ずいぶん姿形が変わっていたようだけれども、髪の色や身長などは、聞くところによるとヒルダのそれと同じだった。さらに死体が身にまとっていたという衣服は、ヒルダがよく着ていたもののようだった。
その後、数日経ったある夕方に、アルマはエーリーンをさそってその橋に行ってみた。さして荒々しくも大きくも見えないのに、これまで何人もの命を飲み込んできた川は、彼女らふたりを前にしても、飄々と流れてゆくばかりだった。ふたりはしばらくそうして、水の流れを眺めていた。
「助けてあげられなかったなあ」
橋の手すりに腕をもたせかけて、アルマは呟いた。
「そうねえ」
長いまつげをふせて、エーリーンが言った。
それからふたりは連れ立って、夕陽を照り返す川の岸辺を、ゆっくりと歩いて行った。
----------
参考url
"The Hand of Glory and other gory legends about human hands," by Prof. D.L. Ashliman