円疵 2
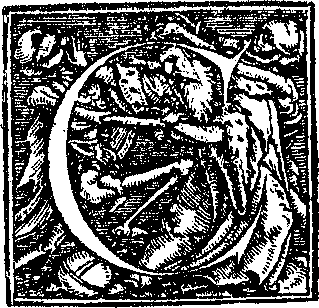 IRCULAR RIPPLES.
IRCULAR RIPPLES.
それから数日後、五日くらいだったかな。おれとそいつは、また例によって雑用で、空になった酒の樽をいくつも倉庫から外に運び出してた。裏口のすぐ外で樽を下ろして身体を伸ばしたところで、そいつのシャツがめくれた。ちらっと見えたその体が真っ赤で、おれはぎょっとしたんだ。
腹だよ。一瞬だけだったが、大やけどでもしたか、でなけりゃ拷問でも受けたみたいに、腹が一面真っ赤に見えた。
おいその腹どうしたと、おれは尋ねた。だがそいつはきょとんとしてる。なんだ、この疵(きず)なら前に見せただろう、なんてって笑ってな。
ちょっと見せてみろと、おれは強く言ったよ。そいつはやっぱりきょとんとした様子で、おれに向かってシャツをまくってみせた。
おれは唖然とした。
丸が。
一面にだよ。
文字通り、“丸”だ。それが腹一面に、こうやって。
五重か六重はあったな。どれも臍を中心にして、同心円ってのか? こう半径一インチ(約二センチ半)くらいの間隔で腹に刻まれてるんだ。外に行くにつれてどんどん大きく深くなってな、いちばん外側のはもう、二の腕の横の、こう脇の下あたりから胸の真ん中あたりをぐるうりと描いて、反対側の胸の脇で消えてる。まだきちんと乾ききってすらいないようで、血が混じった黄色い液がじんわり滲み出て、よく見りゃシャツにうっすらしみを作ってた。半分固まりかけて、ところどころくっついててな。あきらかに一番外側のがいちばん新しい、たぶんその日の朝か前の日の夜に彫られた疵だった。
いったいぜんたい何があったんだ、とおれは呟いたよ。声がかすれちまった。
そいつはけろりとしてたよ。だからあいつとの絆のあかしなんだ、なんて言ってな。あいつのところに戻って以来、毎日こうして一緒にいる日々を刻んでる、おれはあいつをひどく傷つけたから、それでもまだおれと一緒にいてくれるあいつを見ると、自分もそれに応えてやらなきゃならん気がする、とかそんなことを言いやがる。
しばらく声も出なかった。だけどもかすれ声を絞り出して、忠告したよ。やめとけ、とな。本当にその女がおまえに惚れてるんなら、大事な男の身体に毎日傷が増えていくのを喜ぶはずがない、とな。
するとそいつの目の色がさっと変わった。虫でも見るような視線でおれを眺め、
「あいつを悪く言うのか」
と言った。
気味が悪かったが、つとめて冷静を装った。そうじゃない、わざわざ自分を痛めつけて痛い思いをするよりも、精を出して働いて、たんまり金を貯めて、うまいもんでも食わせてやったほうがよほどいいだろう、と言ってやった。
そいつはおれの声を聞いてるのか聞いていないのかもわからん顔で、自分の臍のあたりをじいっと見つめてた。それから、まだ乾いてない外側の円を人差し指の爪でなぞってから、
「うん」
と言った。
そのとき初めておれはわかったよ。あのとき、何もないのかとあいつに聞かれたときに、何もないと答えちゃいけなかったんだとな。おれは阿呆なことに、あいつがぎりぎりのところで綱渡りの綱から落っこちないようにしてた、そのまぼろしみたいなものを吹き飛ばしちまったんだ。腹の上に自分の尾を食いちぎる蛇を見ることで、そいつはなんとか平衡を保ってたんだなあ。その蛇がいなくなったものだから、その蛇のかわりに誰かが自分で自分の首を絞め、自分で自分の手足を食べて腹をふくらませなけりゃならなくなったんだ。もしおれが、おまえの腹の上にはたしかに自分の尻尾を食ってる蛇がいると、そうとだけ言っておけば、あいつ自身が自分の体を食い破り始めなくて済んだはずなんだ。
……気づけばじっとりと脂汗をかいてた。血なまぐさい匂いがぷんと鼻をついたのをおぼえてる。あいつの身体の細いかさぶたからねっとりしみ出す黄色い汁が、おれの汗の穴のひとつひとつからも滲み出て、べたべたと身体に広がっていく気がした。たまらなかった。用事があるのを思い出したとかなんとか、適当なことを言って、おれはその場を逃げ出した。
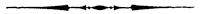
「それがおとついのことだ」
そう言って言葉を切り、ダグラスはエールをあおった。日はすっかり暮れて、出窓の蝋燭の灯りを藍色一色の硝子が反射している。ダグラスのジョッキはとうの昔に空っぽだったようで、舌打ちしてジョッキをテーブルに戻す乱暴な音が響く。テーブルの粗末な木板のはしに這う微細な蜘蛛が、その音に驚いてきゅっと身をすくめた。その様子をデューラムはただぼんやりと眺めていた。
脳裏の水たまりに無音のまま水滴が落ちる。
波紋。
昼間見た灰色の光景がゆっくりと頭の中に広がってゆく。
重くたちこめた雲の下、粛々と運び出される粗末な木棺。小さな窓の内側に叩きつけられていた、ひきずるように尾を引いた茶褐色の手形。戸口を遠巻きに囲む群衆。とぎれとぎれに聞き取れた、あちこちのささやきの断片。
――何があったのか知らないけれども……
――まだ若いのに……
――酷いにおいが……
――もうずいぶん腐って……
――数日前ではすまないとか……
――しばらく生きていたらしいって……
――部屋のなかが血の海で……
――おなかに赤ちゃんが……
――中の子どもごと……
――自分のお臍を……
――お臍を錐(きり)で……
――錐で一突き……
「どうした」
かけられた声に、デューラムはわれに帰った。生唾を飲み込んで答える。
「なんでもない」
ダグラスはその様子を眉をあげて見ていたが、肩をすくめて言った。
「薄気味悪い話だろう。だが旬の怪談は、ここで終わりさ。あいつは一見、何の変わりもなく昨日も今日も仕事に来てる。おれもそのことには触れず、ただ黙々と仕事をしてる」
デューラムは唇を舐めた。唇はからからに乾燥していた。
傷が一面に刻まれた腹をダグラスが見たのがおとついだという。その数日前に男は女に会いに行き、最初の円を身体に刻んで“もらった”。
いや、そんな偶然はあるわけがない、とデューラムは思いこもうとする。だが、……
もしそうだとすれば、その男は何に再会したのだろう。
……と、「おい」と横からかかった男の声に、ふたりは振り返った。視線の先に赤毛の痩せた男が立っていた。ダグラスに軽く手を振ると、しだいに埋まりだしたテーブルや椅子をかきわけてこちらに近づいてくる。
「仕事帰りにここに来てたとは知らなかったぜ」男は言った。「ここは良い店だよな」
「行きつけでね」微笑し何事もなかったかのように答えたダグラスは、デューラムのほうを顎でしゃくって見せた。「こっちは飲み仲間だ」
そりゃどうも、と赤毛の男はデューラムに笑みを向けた。表情こそ人なつこそうであったものの、その目は奇妙に光を失っていた。頬はこけ、ひび割れた唇にはうっすらと血が滲んでいた。飲んでいくかとダグラスが誘うと、男は陰翳の深く落ちた顔に笑顔を浮かべ、
「いや待ってるのがいるんでね」
と答えた。
その痩せた顎の下で、暗い赤色の線がぬらりと光る。麻のシャツの襟口からかろうじて覗くその傷は、鎖骨のすぐ下あたりに細いながらも深い曲線を描き、室内のかぼそい灯りに濡れた色を放っていた。
最も外側の。
最も新しい円。
――毎日一緒にいる日々を肌に刻んでる、なんて言ってな、……
お臍を錐で。
錐で一突き。
そうして、デューラムはそのとき、たしかに見たのである。その男の臍から真っ赤な血潮があふれ出すのを。豊潤にほとばしるその赤波が粗末なシャツを染め、さらに男の身体一面に広がってゆくのを。形を失った雪がしたたり落ちて水たまりに描く波紋のように、いくつもの円が裸の肌に刻まれていくのを。中心からとめどなく湧き出す無数の美しい同心円は、そのどれもが小刻みに蠕動する粘膜となって、蝋燭の灯りにその表面をてらてらと光らせ、腕から手へ、胸へ喉へと広がってゆく。
赤い円に溶ける男の全身が、風に薙ぐ水面(みなも)の影のごとくその形を曖昧にする。男の笑顔がぐにゃりと歪む。蛇があぎとを開く。巨大な波紋のなかに、すべてが呑み込まれてゆく……、
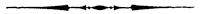
どのくらい時間が経ったのか、デューラムにはわからない。
気づけばいつしか彼は先程までのように、大衆酒場の一角で背中を丸め、ダグラスと顔をつきあわせ、テーブルの上をぼんやりと眺めているのだった。
男はすでに去っていた。
ダグラスがぽつりと呟いた。
「あいつはもう長くないのかもしれんな」
ぷうんと生ぐさい匂いが鼻をついた。
読んだよ報告にでも ↓
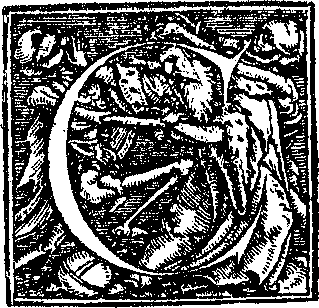 IRCULAR RIPPLES.
IRCULAR RIPPLES.
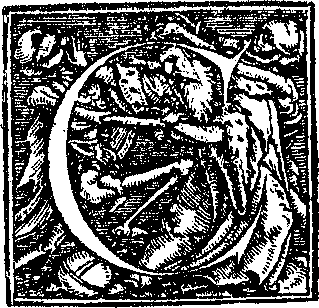 IRCULAR RIPPLES.
IRCULAR RIPPLES.