円疵
1
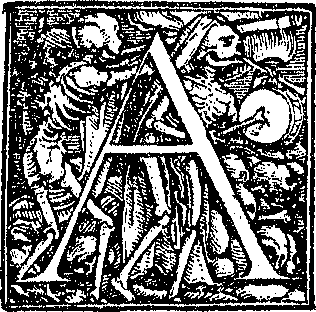 CIRCULAR SERPENT.
CIRCULAR SERPENT.
冷たい音を立てて枝から落ちたしずくが跳ねた。夜半に枝々に積もった雪が午(ひる)すぎの気温に溶けて、透明な水を地面に滴らせているのだ。道脇の樹木の下に広がる大きな水たまりに静かな波紋が広がっていく。均整の取れた美しい波の同心円を、デューラムはぼんやりと眺めていた。
昨晩、夜更けから降り出した雪は朝になってみぞれに変わり、いまは氷混じりの冷たい雨となって、街の一角に集まる人々の外套と靴とを重く濡らしていた。中央の二つ・三つの黒ずくめの姿を除き群衆の大半は普段着の町民で、したがって彼らもまたデューラムと同じように、人だかりのささやきのなかに血なまぐさい単語を聞きつけて、思わず足を止めた無関係の輩にすぎないのだった。
家と家とが壁をくっつけあってひしめく下町の一角の、その扉から出てきたのは粗末な木棺だった。棺を抱える四人の男たちは墓所か寺院に雇われたといったふうで、棺のなかに横たわる何者かの関係者とも見えなかった。男たちの後から戸口をくぐり抜けた神父は、静かに振り返ると胸の前で神へのみしるしを刻み、忌みを祓い、そうして去っていった。
棺が市壁の外の共同墓地へと運ばれていくと、声をひそめて興味本位の噂をささやいていた群衆も、また一人、また一人と消えていく。デューラムは歩き出した。
その日は灰色の空がヘプタルクの都をいちめんに覆いつくしていた。見上げればひっきりなしに顔を打つみぞれの源は、しかし白く濁ってあてどもなく広がる雲ばかりである。道を行き交う人々はみな足早に歩みを進め、知人と出くわしても簡単な儀礼文句のみで別れを告げ、浮かない顔つきでまた目的地に急ぐのだった。輝きのない湿った景色のなかに取り込まれてしまうのを、誰もが恐れているかのようだった。
そのうちデューラムが歩き着いた行きつけの酒場は、まだ時間が早いこともあって、人影もまばらだった。いつもよりずっと静かな店の隅に、見慣れた大きな影が座っている。デューラムはそちらに足を向けた。
「今日はおまえひとりか、ダグラス」
横からかかった声にダグラスは振り向くと、頷いた。「しけてやがる」
「天気も酒場もどいつもこいつも湿っぽいとはな」デューラムは肩をすくめた。「こういう天気だからこそ、ぱあっと騒いで辛気(しんき)の虫を吹き飛ばさなきゃいけないってのに、みんなじくじく家に閉じこもってるのか」
ダグラスは肩をすくめた。「……まあ、気持ちはわからんでもない。冬の終わりの雨はいつだって陰鬱だ。きりっと冷え込んだ真冬の朝や荒っぽい吹雪のほうが、まだなんぼか身が引き締まるってもんだ」
「なんだ、珍しくしけたツラをして」とデューラムは笑った。「気の利いた噂話や怪談のひとつやふたつでも無いのか? みんなに聞かせるのがもったいないようなネタを、このさいおれだけに披露しちゃどうだ」
ことさらに陽気な口調でそう言ってやると、ダグラスはあいまいに笑った。
「怪談なら、最近仕入れたとっておきのやつがあるぜ。聞きたいか」
デューラムはがたんと椅子を鳴らし、ダグラスの向かいに腰かけた。「旬の怪談か。いいぜ。聞こうじゃないか」
ふんと鼻を鳴らすと、ダグラスはすでに空になっていたエールのジョッキを掲げてみせた。「とりあえず酒を買ってこい。怪談話はいい酒の肴だが、肴だけじゃ話は始まらん」
苦笑したデューラムが自分と相手と二人分の酒を持ってくると、ダグラスは渡されたジョッキにひとつ口をつけて、そうして話し始めたのだった。
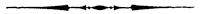
二週間前、知り合いに頼まれて、ひとつ臨時の仕事が入ってな。
急に人が抜けたってんで、次を見つけるまでのあいだ、昼間のちょっとした時間だけ働いてくれってことだった。
おれもふだんの仕事はその時間帯に入っていなかったし、少しの期間だけなら小金稼ぎにもいいかと思ってな。引き受けることにした。
そいつは珍しい酒だの香料だのを金持ち向けに売ってる商人の仕事場でな。お高い酒をわんさかつめこんでる倉庫に裏口から変な奴が入り込んだりしないよう、そこに突っ立ってガードするのが主な仕事だった。
だが、それほど治安の悪い場所でもないしな。その戸口が面してる裏通りだって、洒落た服を着て気取った奴らが近道をしようと通りかかるくらいなもんだ。スリやこそ泥なんてのはあんまりうろちょろしてやしねえのさ。そんなわけで、おれもな、酒の瓶だの酒樽だのを馬車から倉庫に入れたり出したりするのを手伝ってる。力仕事をする人間がほかにあんまりいないんでな。
その店に、おれと同じような仕事をしてるやつがもう一人いてな。
赤毛で中肉中背の、人当たりのいい男だ。
だがひとつだけ欠点があってなあ。そいつ、事あるごとに別れた女の話ばかりしてやがるのさ。
とにかく頻度が度を超してる。ずいぶん惚れてたらしい。未練たらたらさ。女々しいったらありゃしねえよ。
どんな女かって? はは、おれも尋ねたよ。いい女だった、いい女だったってあんまり繰り返してるもんでな。黒くて細かな巻き毛の、ふっくらした女だったってこったよ。腰と太股のあたりに小気味いい曲線でむっちり肉がついていて、それが色っぽいんだとか言ってたな。
なんだ、べた褒めだって? そうさ、べた褒めさ。そんでその女がまた、器量もよけりゃ気だてもいいときてる。とにかく一途で、ほかの男に色目を使うことなんかもないし、そいつがちょっと遅くなると心配そうにいつまでも寝ずに待ってる、そんな女だったんだそうだ。
さっき、そいつが女々しいって言ったろう。いちばん女々しいのはな、そいつの愚痴り方なんだ。あんないい女はおれにもったいなかった、釣り合っていなかった、幸せにしてやれる男がほかにいる、とかそんなことばかり繰り返してやがる。もう聞いてるこっちが痒くなってくるじゃねえか。未練があるならよりを戻しゃあいいし、釣り合ってないと思うんなら忘れりゃいい話だ。しゃきっとしろと言いたくなるだろう。
まあ、それはいいとしてだ。そいつによりゃあ、その女、一個だけ変わったところがあったんだそうだよ。
何かって?
尖ったものがな。
尖ったものが、むやみに好きだったんだそうだ。
なんだそりゃあって顔を今したな。おれだってそう思ったよ。尖ったものが怖くてたまらんという奴が世の中にいるってのは聞いたことがあったけどな。ペン先を見てると目に刺さりそうで怖いとかっていう、あれだ。ナントカナントカっていう長い呼び名をツァランの奴が言ってた気がするが、忘れちまった。
いずれにせよだ、その女は逆なんだ。喋ってるあいだ手持ちぶさたになったりすると、何か尖ったもので自分の手を延々と突(つつ)いてる。かるーく、かるくな、血も出ないほど軽く傷を付けながら、手の甲だの腕だのにひっかき傷の絵を描く。なんでも、とがったものが肉のやわらかいところに、薄皮一枚破るか破らないかの瀬戸際で食い込んでる感触が、ぞくぞくしてたまらないんだそうだ。まあそれだけならいいんだが、道ばたに落ちてた針金を拾ってくる、金物屋に行って必要もないのに新しい錐(きり)を買ってくる。そんでもって集めたもんを専用の箱に入れて取っておく。変わってるというか、正直言うと、ちょっと不気味じゃねえか。
まあ誰にでも癖はあるから、毎日の生活に差し障りが出るわけでもなけりゃどうこう言う筋合いも無いがな。毎日毎日見てるとイライラしてくる癖もあるかもしれないからな。別れた経緯にはそんなことも少し関係してたのかと思いながら、おれは適当に相づちを打って聞いてたよ。
そんなある日だった。
ちょっくら仕事が長引いた日に、ふたりで飯(めし)を食いに行ったのさ。それがまた、ちょっとうまいエールを作る店でな。ほろ酔い加減で雇い主の商人の悪口なんぞを言ってたら、そいつがまたしても別れた女の話をおっばじめやがった。おれもちょっとうんざりしてな、おまえを捨てるような女ならそれはそれで縁がなかったんだ、たいした女じゃなかったと思ってさっさと諦めちまいなと言ってやったよ。
そしたら、そいつがなんとも言えない顔でうつむいた。こう、唇噛みしめて真っ白にしてな、頬なんぞぷるぷる揺らしてな。おれもさすがに驚いて、すまん口が過ぎたと謝った。
そしたらそいつが言うんだ。違うって。
違う、ダグラス、おまえが悪いんじゃない。あいつに捨てられたんじゃない、捨てたのは自分のほうなんだってな。
てっきりこっぴどくフラれたもんだと思ってたからな。おれは思わず聞いた。そこまで惚れてたのに、なんで捨てたんだって。
そしたら、そいつは答えたよ。
怖くなったんだってな。
その女がさ。
そうして、そいつはこんな話をしやがった。
まだふたりで住んでた頃、ある晩ふたりで寝床に入って、それで、まあそういう雰囲気になってだな、色々と二人でしたわけだ。ことが終わって女に腕枕をしてぼんやりしていると、裸の女がおもむろに身体を起こしてな、そばにあった机の引き出しから錐を取り出した。そうして、そいつの腹に覆い被さったというんだ。
そいつもびっくりしてな、おい何をしやがると言ってやめさせようとしたらしい。だが女は目をくりくり光らせて見上げてな、動いちゃだめ、刺さったらどうするのって言った。お願い、痛くしないから、薄皮にちょっと傷をつけて絵を彫るだけよ。入れ墨よりか浅いんだから、ねえいいじゃないってな。そう言ったそうだ。
たかが恋人同士のお遊びだからな。そいつも怒るのがばからしくなって好きなようにさせたらしい。すると女は目を輝かせて、そいつの腹の上、ちょうどこう臍のあたりにな、錐でごく浅い疵をつけはじめた。
そいつはむず痒いのをこらえて目をつむってた。だが、とある一瞬ちくりとだけ痛みが走ってな。思わず目をあけて女の顔を見たんだそうだ。
そうしてぎくりとした。
そのとき窓から差し込む月明かりのなかに見えたのが、まったく見ず知らずの女の顔だったっていうんだな。そいつの腹に錐をつきつけてる女がだよ。黒い瞳も黒い巻き毛も変わりはない。だが、異様に青白くふくれあがったその顔も、それでいて落ちくぼんだ眼窩も、どう見てもそいつが惚れた女のもんじゃなかった。ぽってりした唇がぴくぴく痙攣して音もなく何かを呟いてたのと、月明かりのなかに瞳がぎょろぎょろ動いているさまを、いまでもよく覚えてるとそいつは言ったよ。
そいつは悲鳴を押し殺した。相手は一突きで頭蓋骨も貫けそうな錐を自分の臍に突きつけてる真っ最中だ。いま気づいたことが知られれば、その瞬間、このえたいの知れないものが自分の腹に刃物をおっ立てるような、そんな気がしたそうだ。気づかなかったふりをしよう、そうすれば助かると、唾を飲み込んで恐怖を耐えた。
しばらくすると女は錐をのけてな、できたわよと言ったそうだ。まじまじと見返してみれば、いつもの女だった。マアどうしたの、ひどい顔色、肝っ玉が小さいのねえなんてそいつを笑い飛ばしてな。
腹を見てみると、臍を取り囲むようにして一匹の蛇の絵が描いてあった。
丸い蛇だ。
丸い蛇ってなんだって? ううん、蛇が丸くなって自分のしっぽを呑み込んでる絵があるだろう。なんか名前があるのか、あれは? あの蛇が臍の回りを取り囲んでる絵が、肌色よりうっすらと赤く盛り上がった程度の軽い傷になって、自分の腹に描かれてた。女の言ったとおり皮一枚を傷つけてるだけだから、もう痛みも何も感じなかった。ちょっと痒いだけだ。
それでも、ぞっと背筋に寒気が走ったんだそうだ。たいして上手くもないその蛇の、どこを見てるとも知れない無感情な目が不気味だった。まさにその女とついさっき絡み合って流した汗が、突然すうっと引いて身体を冷やした。ねえ上手でしょと女が聞いてくるので、男はあいまいに返事を返すと、毛布に潜り込んで、寝たふりをした。
その翌朝、まだ夜も明けるか明けないかという時刻にな、そいつは手近な荷物をまとめてこっそり家を抜け出した。別れも告げず、手紙も残さず、ただ数日分の服と金だけ持ち出してな。ぐっすり眠っている女の腕をすりぬけて寝台から降りるときも、音を立てないように扉を閉めて朝の霧のなかに走り出したときも、なぜ惚れた女から自分が逃げだそうとしているのか、よくわかっちゃいなかった。ただ、前の晩に見た黒ぐろとした底なしの目玉が、目を閉じるたびにまぶたの裏でぎょろぎょろ動いてこっちを見てた。それが怖くてたまらなかったんだそうだ。
そうやって家を出て数日経った。すると、女を捨てて家を出るなんて馬鹿げたことをしたという気持ちがどんどん強くなってきた。働き者のあんないい女から、何も言わずこそこそ逃げ出した自分は無責任で甲斐性なしのろくでなしだと思った。一瞬、光の加減で女の顔が変な風に見えたからといって、何年もの縁を切るなんて馬鹿げてる。何度も戻ろうとそう思った。
それでも戻れなかったんだそうだ。
何故かって?
そいつは言うんだ。
疵(きず)が消えないんだと。
女が描いた蛇が腹から消えないんだと。
そいつは皮一枚を傷つけただけの、疵とも言えない疵だから、二日三日も経てばきれいに消えてなくなるはずだった。それが半年たった今でも、ぼんやり残ってるというんだよ。
おれはごくりと唾を飲んだよ。そうして、見てもいいか、とそう聞いた。
野郎の腹なんぞわざわざ見たがる趣味はないが、事情が事情だった。やつの語り口も、怯え方も、そのくせ女にひどく執着してるその齟齬も、何もかも奇妙だった。おれはその蛇とやらに好奇心がかき立てられてたのさ。やつが頷いて麻のシャツをまくりあげたんで、そいつの腹を覗き込んだ。
何があったと思う?
なんにもなかったんだよ。
ごく普通の腹だった。
蛇どころか、臍の回りにぼんやりした痣すらできちゃいなかった。
笑っちまったよ。何が見えると思ってたんだと、自分でも今となっちゃ馬鹿馬鹿しいが、見ず知らずの顔に化ける女だの、錐で身体に描いた蛇だの、そんなおどろおどろしい話をそいつがするもんで、おれもそのときは雰囲気に呑まれてたんだ。
なんだ、何もないぞ、おまえの気のせいだと言ってやった。明日その女のところに戻ってみろよ、ひょっとするとまだ独り身かもしれねえぜ、とな。
そいつは疑り深げにおれを見返した後、自分の腹を自分で覗き込んだ。それから、こう言った。
「何もないのか」
何もないぜ、とおれはもう一度言ってやった。
まるで十年背負ったまんまだった重荷を下ろしたような表情をそいつが浮かべたのを、よく覚えてるよ。
それから二日・三日、店は休みでな。おれらも顔は合わせなかった。休み明けにまた店に出たらな、そいつが妙に晴れ晴れした顔をしてやがる。どうした、さては女に会いに行ったなと言ったら、やつは嬉しそうに笑ったよ。
そうして、見ろと言ってシャツをまくり上げるじゃねえか。
そしたらだ。
疵があるんだよ。
そうだ、丸い疵だ、下腹のあたりにな、こう臍を取り囲むようにして。
ただし、あいつが言ってた蛇じゃあない。普通の、ただの細い線の円だ。それが臍のまわりに赤くかさぶたを作ってるんだ。
おれは驚いて聞いたよ。いったいこいつはどうしたんだ、とな。
そうしたらやつは言った。
もうその女のことを捨てない証に、もう一度疵を描いてもらったんだ、とな。
前と同じように、錐で身体にしるしを刻んでもらったんだ、とな。
おれは呆れたよ。女が女なら、男も男だ。おまえらはまったくお似合いだよ、とそう言ってやった。
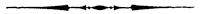
雨は相変わらず降り続いていた。水滴がひっきりなしに吸い付いては垂れる酒場の窓硝子は、夕刻の到来にその色をどんよりと暗くしていた。
デューラムは苦笑した。「なんだ、……まあちょっと変わってるが、そいつらにとっちゃ入れ墨みたいなもんなんだろう。おたがい惚れ合った馬鹿なふたりがよりを戻して、のろけ馬鹿になって、めでたしめでたしじゃないか」
ダグラスはデューラムをちらりと見ると、二の腕に彫られた唐草文様の入れ墨をぼりぼりと掻いた。それから腕を改めて組み直す。
「おれもここで話が終わっていれば、そう思ってただろうな」
少しの沈黙をはさんで、デューラムは尋ねた。
「終わらないのか」
「終わらん」ダグラスは答えた。「驚いたのは、その数日後だった」
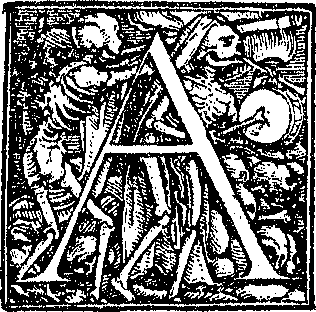 CIRCULAR SERPENT.
CIRCULAR SERPENT.
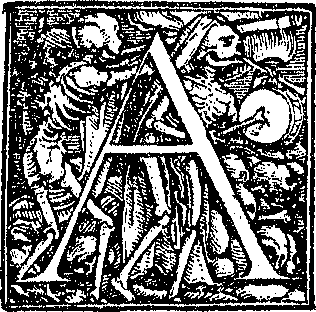 CIRCULAR SERPENT.
CIRCULAR SERPENT.