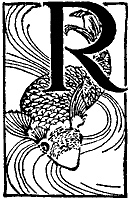 ACE IN THE DAWN.
ACE IN THE DAWN.
弟が駆け出して行った戸口を見つめて立ち尽くしていた兄は、それからゆっくりと娘をふりかえりました。娘は毛布でからだを覆いかくすようにして裸の肩を震わせておりました。
兄はそんな妻にむかい、これはどういうことかと尋ねました。静かな声でした。娘はうつむき、かすれた声で、とぎれとぎれに語り出しました。――今朝みなが漁に出た後、あれはふらりと家にやってきた。朝と違う着物を着ていたものだから、最初は娘も夫が戻ってきたのではなく、弟が訪ねてきたのかと思った。しかし少しやつれた顔こそしていたけれども、喋り方も表情も彼女への接し方も、みな弟ではなく夫のそれに相違ない。疲れたから仕事を抜けて出てきた、服は潮でぬれそぼってしまったので弟に借りたのだと、あれはそう言った。次いで、すぐに仕事に戻るから、ほんの少しだけ休ませてくれと、そう言って、籠を編んでいた彼女に寄りかかったのであると。娘はいつもと異なる夫の姿に驚きながらも、働き者の夫といえどもたまにはそのようなこともあるかと思い、求められるままにおのが肩を貸したのであると、……
娘の見開かれた両の目からぽたりぽたりとふたつの涙が落ちます。その様子をぼんやり眺めていた兄は、しばしあって、やはり静かな声で、きょうがはじめてか、でなければ何度目かと尋ねたのでございます。
娘はびくりと竦むように目をあげました。
兄はそんな妻を見て微笑しました。そして、わからぬか、区別がつかなかったのなら、と言いました。それから娘が答えるのを待たず、ふらりと家を出ていったのでございます。
その夕べのことでした。ふたごの兄はその語り手の老人――彼の人のところを訪ねたそうにございます。家を出て行ったあの時からずっと漁でもしていたのか、びくにいっぱいの魚をたずさえてやってきた兄は、魚を突くときにいつも使っている手銛もその手に持ったままでした。今日は大漁だと笑うそんな兄の心情をさっして、彼の人はとっておきの酒を棚から下ろしたのでした。
兄の取ってきた魚はいずれも立派なもので、とろりと脂がのって酒と調和し、それはみごとな味でした。肴に舌鼓を打ちながらふたりはしばし歓談しておりましたが、そのさなかにふと沈黙が下りたのだそうでございます。彼の人は空になった兄の杯に酒をそそぎながら、どうするつもりか、と尋ねました。兄は杯を口に運び、くちびるを拭ってから、さあなと一言答えたのでした。
そのうちふたりもよく酔って、酒や肴もそのままに、いつしかむしろの上で寝入ってしまったようでした。そして真っ暗闇の中、彼の人はがたんという音で目をさましたのでございます。見れば、卓の向かい側で同じく寝入っていたはずの兄が立ち上がり、家を出て行こうとしているところでした。どうした、朝まで寝ていけよと彼の人は声をかけました。そうして振り返った兄の顔を見て、ぎょっとしたのです。兄の目は真夜中の闇の中でらんらんと光り、激しくうねる情の炎に燃えておりました。そうして、弟が、弟が、あいつをさらって今逃げようとしていると、そう唸ったのでございます。
彼の人はすっかり驚いてしまい、そんなことがなぜわかる、さては泥酔して錯乱したかと、兄を止めようとしたそうでございます。ところが兄は恐ろしい力で彼の人を振り切り、わかる、わかる、今あの二人が浜を逃げて行くのだと一声叫ぶなり、弟に贈られたあの手銛を床から拾い上げ、家から飛び出していったのでした。
あの目の色はただごとではない、刃傷沙汰にでもなればことだと、彼の人は続いて家を飛び出して、懸命に兄のあとを追いかけました。酒に酔い錯乱した者の足取りとは信じられないほど、兄の走りは飛ぶように速く、見失わないのが精一杯でした。兄は自分の家を確かめる事もなく通り過ぎ、砂浜が険しい磯になり集落が途切れる村境に向かって、一直線に走ってゆきます。そうしてそれを後から追う彼の人も、刻々と近づく夜明けの薄明かりのもと、大小二組の真新しい足跡が砂に刻まれているのを見たのでございます。兄の前を、男と女の二人組が走って逃げてゆくのでした。
どうどうと海が沖で唸っておりました。西半分を覆う空の黒は、東に行くにつれてまるで墨を薄めたように淡く、薄くなって、その東の青灰色の空のまんなかに、血がしたたりそうに細くとがった月が刻まれておりました。彼の人の前をゆくふたごの兄の、そのさらに向こうの岩場で、つまずきながら先を急ごうとするふたつの影が見えます。さきをゆく影が小さい影の手をひいておりましたが、険しい岩場に足をとられ、思うように進めないと見えました。
兄は砂を蹴って走りながら、弟の名を高く長く叫びました。影のひとつがはっと振り返ります。逃げられぬと悟ったか、女を横の砂地につきとばし、弟は迫ってくる兄にたいしてみがまえようといたしました。
そこに追いついた兄は、手にしていた銛を投げ捨てるなり、こぶしを握りしめて弟を激しく殴りつけました。弟は大きくたたらを踏みましたが、きっと向き直ると、反撃とばかりに兄にとびかかりました。それから、背格好もうりふたつの若者たちは、取っ組み合い、もつれあい、砂の上をころげまわりながら、たがいを殴りつけ、痛めつけました。ようやく兄に追いついた彼の人も、その乱闘の激しさと、なによりそこからにじみ出る怒りと憎しみと、うねりあう情の強さに、ただふたりを眺めるほかなかったそうにございます。ざあん、ざあんと黎明の波を響かせる暗い海のまぎわでねじれあい、ぶつかりあうふたつの影の、どちらが弟でどちらが兄なのか、もう彼の人にもわからなくなっておりました。
どれほどその乱闘が続いたときであったでしょうか。一方が上にのしかかっていた相手を強く跳ね飛ばしたのでございます。はねのけられたほうは後ろに大きくよろけ、ぐらりと倒れこみました。そうしてその背後には、黒く険しい岩場があったのでございます。
にぶい音がいたしました。倒れた影は、ひゅうと喉から笛のような音を鳴らしたきり動かなくなりました。突き飛ばしたほうの影はさっと起き上がってみがまえましたが、相手がかかってくる様子はございません。彼はいぶかしげに、上半身をだらりと岩場にもたせかけた相手に近寄りました。そうして、その相手の耳と鼻からどろりと黒いものが流れ出ているのを、そして見開かれたままの瞳がすでに何をも見ていないのを、知ったのでございます。
若者はしばらく、倒れたきょうだいを見つめていました。それから横に倒れ込んだまま震えている娘を見、少し離れた場所に立ち尽くしたまま呆然としている彼の人を見ました。それから彼はおのが片割れに視線を戻しました。ううう、ううう、という低いうめきが彼の口からこぼれ出ました。はらわたが握りつぶされたような、低い、しわがれたうめきでした。おお、おお、死んでしまった、いってしまった、死んでしまった、と若者は呟きました。それからのちは、たった一瞬の出来事でありました。彼はそばに転がっていた手銛を素早く拾い上げるなり、彼の人がとっさに飛び出して止めようとするも間に合わず、そのするどい銛さきを横から一気におのが喉に突き通したのです。
若者の喉から弧を描いて吹き出した血は、夜明けの青白い闇のなかでまるで藍の染汁のように見えたと彼の人は申しました。それから若者は膝を折り、ぱたりと砂の上に倒れたのでございます。
彼の人は若者に駆け寄りました。けれども若者がすでに絶命しているのはわかりきっていたのでございます。岩場の上に倒れ死んでいるきょうだいとまったく同じ目で、若者は砂の上から虚空を見つめておりました。若者の首あたりからとめどなく溢れでるものが、周囲の白砂を丸く、黒ぐろと染めあげてゆきました。
あまりのことにこぶしを震わせながらも、彼の人は娘を振り返りました。娘は先ほどと同じように、少し離れた砂の上に座り込んでおりました。明け方の空の色をしたおぼろげな瞳に、このときだけはくっきりと、ついさっきまで自分を取り合ったふたりの男であったもの、そして今となっては磯と砂の上に転がるしかばねにすぎなくなったものが映っておりました。しばし呆然としていた娘は、ふと気づいたように彼の人に目を向けました。そして一言、死にました、とだけ呟いたのでございます。そして次の瞬間、娘は砂の塔が崩れるように倒れ込んでいたのでした。
朝日が昇ろうとしていました。彼の人は娘をかついで村へと戻り、ふたごが死んだことを村人に知らせました。それから彼は小さな舟を出し、きょうだいの体を沖へと運び、ふたり一緒に海へ流しました。見開いた目に青い空とたがいの半身とをかわるがわる映しながら、ふたつのしかばねはゆらりゆらりと手足を揺らし、深い水の底へと沈んでいったのでございます。
ただでさえ寡黙だった娘は、それからのち二枚貝のように口をとざしてしまいました。たったの一言をも発する事なく、娘は貝をとり、海藻をとり、時おり波の音を聞くように磯に腰かけて海を見つめながら、夫のいなくなった家でひっそりと暮らしつづけたそうでございます。そうしてまた彼の人も、何がふたごを死に導いたのかをふしぎと誰にも話す気になれなかったそうでございます。ですから、一部始終を知っているのはいまや彼の人と娘だけなのでした。
娘の腹のふくらみが目立ち始めたのは、それから三月ほどたったときのことでした。そして、ふたごがいなくなってからかっきり九月の後、彼の人の妻の手伝いのもと、二日にわたる苦しみののちに、娘はそれを産み落としたのでございます。
ええ、それと申しました。子と呼びうるものでは到底なかったのでございます。娘が時折の痛みにうめくかすかな声と、それを励ます妻の声が途絶えて、少したったときのことでした。家の外で仕事をしていた彼の人が聞いたのは、赤子の声ではなく妻の悲鳴だったのでございます。驚いて家の中に飛び込んだ彼の人が見たのは、驚きと恐れにゆがんだ妻の顔でした。お産でどこかが裂けたのか、部屋の真ん中には血の池ができており、妻はそのすぐそばで腰を抜かしているのでございます。そしてその妻の前、娘の両のふくらはぎのあいだに転がっていたのは、まさに人の赤子ほどの大きさの黒ぐろとした海藻のかたまりだったのでございます。娘の目は安らかに閉ざされておりましたが、両手両脚はだらりと生気なく投げ出されておりました。すでに事切れていたのでございます。
彼の人はふらふらと床に膝をつき、娘が産み落とした黒い塊を見つめました。そしていつしか気がつけば、何かに憑かれたかのように、そのからまりあった海藻をほどいていたのだそうでございます。娘の腹から流れ出た水と血とでぬめる海藻を一枚、また一枚とはがしつづけ、どれほどの時間が経ったでしょうか。海藻の中央からころりと小さなものが転がり出ました。呆然としていた彼の人の妻が、ふるえる指でそれを取り上げます。
そして、ああふたごの烏貝(からすがい)だと、そう呟いたのだそうでございます。

「それがこの烏貝なのですか」
アルマは硝子びんを持ち上げ、もう一度中をのぞきこんだ。
「はい」
女はうなずいた。「それ以来、彼の人はその烏貝をこうしてびんに入れて、ずっと置いていたそうでございます。けれども自分もすでに老い先が短いからと、迎えが来る前に誰かにこの一部始終を話しておきたかったのだと、そう言ってわたくしにこの貝を託したのです。誰かに譲るなり、海に流すなり、好きにしてよいと彼の老人は申しました。けれどもそれから二十年、なんとはなしに手放す気になれず、ずっとこうして持ち歩いてきたのです」
そう言って息を切ると、女は微笑した。
「……とるにたらぬ昔話でございます。とりとめもなく長々とお話をいたしまして、さぞご退屈だったでしょうに」
いえとアルマは首を振った。「ふしぎなお話です。その娘さんは結局なんだったのかしら。そして、この烏貝はその双子のどちらかの子どもということになるのかしら……でなけりゃきっと、兄弟がもう一度生まれ変わって一緒になったものなのかもしれませんねえ」
言いながら、アルマはカウンタの上の硝子びんを見下ろした。己の由来が話題になっているのもそしらぬ顔で、ふたごの貝はびんの底でゆらゆらと揺れていた。
「……だけども、ひとつ、お尋ねしてもいいですか」
少し間を置いてから言ったアルマの声に、女は少し顔を上げた。
「その娘さんが何を考えていたのかって、ご老人のお話の中ではよくわからないですよね。島に流れ着いて、兄弟ふたりに好かれて、選ばなかった人にだまされて、夫を裏切るように差し向けられて。そうしてまるで物みたいに夫のところから奪われて、連れて逃げられて、その女の人はいったい何を考えていたのでしょうね」
そこで言葉を切ってみたが、女は答えなかった。アルマは少しためらってから、さらに続けた。
「でもそのひと、ほんとうにわからなかったのかしら。いくらそっくりだったとは言っても、一年もいっしょに暮らして寝起きをともにしたのに、体まで合わせた人の区別がほんとうにつかなかったのかしら。それとも、ほんとうはわかっていたのかしら。自分がからだを差し出した相手が夫ではなく弟だったことを」
女は変わらず黙ったままだった。じっとカウンタの上に置かれたびんを見つめている。あまりに長く続く沈黙にアルマはそのうち気まずくなって、やはり下を向いて少し笑った。そして、変な感想ですよね、きっと突っ込んで考え過ぎなのねと続けようとした。
そのときだった。ことりと音を立てて、何かがカウンタの上に落ちる気配があった。思わず目をまたたいたアルマは、外套に身を包んで立つ女のすぐ前に、小指のつめほどの大きさの桜貝が転がっているのを見たのである。
先ほどの藍の布包みに入っていた貝のひとつかと、アルマはとっさにそう思った。だが女はすでに布包みをすべてしまいこんでいたはずだ。一瞬前までたしかにそこにそんなものは、……
またことりと音を立てて貝がらが落ちた。驚くひまもなく次いで三個目がまた落ちて、ふたつの貝がらにぶつかりかちんと震える。さらにもう一個。そしてもう一個、またもう一個、……
「ああ」
女が言う。震える声だ。
「そうです。そうです。そのとおりでございます。六十年前のあの朝、夫としてふるまうあの男を家に入れたとき、娘は知っていたのですわ。それが夫ではなくその弟であるということを。なぜなら娘は兄を選んだとき、弟がやがて自分を奪いに来るであろうことを、すでに予期していたからでございます。だからこそ娘は兄を選んだのですから」
アルマは呆然としていた。ただ立ちつくし、いままさに目の前で起きていることを凝視するばかりだった。たえまなくカウンタに落ち続ける桜色の貝がらは、まごうことなくカウンタの前に立った女の、なかば覆い隠された顔からこぼれ落ちているのだった。フードの影になった両の目からしたたり落ちる涙のように、桃色がかった透明の桜貝が、いくつもいくつもとどまることを知らず落ちつづけている。ことん、からん、こつんという軽く乾いた音とともに、またひとつ、またひとつ、薄桃色が広がってゆく、……
「……娘は選べなかったのでございます。あの兄と弟が、どちらが娘を得るべきかをみずから決められなかったように、娘もまた、兄と弟のどちらを伴侶とするかを決められなかったのでした。両方が欲しかったのです。きょうだいと長く寝食をともにした娘は、兄と弟の気性をよく知っていました。喜怒哀楽を躊躇なく見せる兄が、実のところ理(ことわり)の人であり、村と夫婦(めおと)の掟の前ではためらいなく自分を諦めるであろうことも、もの静かな弟の内部に激しく荒あらしい気性が横たわっていて、たとい兄を選んだとしても弟が自分を諦めることはないであろうことも、みな知っていたのでございます。だからこそ、ふたりのどちらをも自分のものとしておくために、娘は兄を選んだのですわ。けれども、それがなんになったでしょう。最後の最後で結局あのひとはきょうだいを選んだのですから。娘とともに生きることではなく、きょうだいとともに死ぬことを選んだのですから。
そうです。そうだったのです、今わかった気がいたします。あれは罰だったのでした。ふたりをともに欲し、それによってふたりをともに裏切り、ふたりを死にいたらしめた咎(とが)を受けて、娘はふたりをもう一度おのが腹から産み落とすことになったのです。もの言わぬ貝となったがゆえに、けして自分を許すと言ってくれることのないふたりのきょうだいと、この世をさまよいつづけるさだめとなったのですわ。その旅路こそが娘に課された責め苦だったのでございます。北へ、西へ、そしてまた西へと、砂漠を超え森を超え、もの言わぬこの貝にゆるしを乞うてきた、この旅路こそが……」
どこまで女の話を理解していたのか、否、どこまで女の話が耳に入っていたのか、アルマにはわからない。ただ彼女は目の前で開けてゆくふしぎに心を奪われて、その視覚も聴覚もぼうっとなってしまっていたのだった。ことり、からん、こつんという音のなかで彼女の意識はくるくると回転し、かと思えば、ぬめる桃色の光の波にざあと押し返され、また押し流されてゆく。……ふと、磯の香りをアルマは嗅ぎとる。どこから漂ってくるのだろう。女の外套からか。その懐にひそんでいる死んだ巻貝の奥からか。あるいは女の腹の中の羊水をまだその身に秘めながら、数十年を生き続ける小さなふたごの烏貝からか、……
と、アルマはまばたきをして、揺れる意識を呼び戻した。ざわりと視界がさざ波を立てた後、すぐにいつもの通りの店内を映し出す。
店の中には誰もいなかった。
アルマは慌ててあたりを見回した。立ちくらみがしたのはほんの一瞬のことだ。言葉の通りまばたきひとつしている間に、あの女客は去ってしまったというのだろうか。
「お客さん?」
アルマは走って行って戸口から外を覗いてみたが、暮れゆく西日が建物の影を通りに長く落としているばかりで、全身を外套にくるんだあの小柄な女の姿など、どこにも見つかりはしなかった。
アルマは首をかしげながら店の奥に引き返した。先ほどのとおりにカウンタの向こうに戻ったところで、壁際に置かれた小さな硝子びんを見つける。
ふたごの烏貝が入った硝子びんだ。
そしてその横に、小指の爪ほどの大きさの桜色の貝がらが、たった一個だけ、ぽつんと転がっていた。
思い返してみれば、どれもみな確かなことではない。自分は異国の語り手の不可思議な幻術にでもかかって、つかのまのまぼろしを見ていたのではないかという気がする。でなければあの女が店に訪れたことさえもが、じつのところ白昼の夢のようなもので、この珍しい烏貝は誰かほかの客がついでに置いていったものだったようにも思えてしまう。それほどまでに、あの女の話も、あの女の記憶そのものも、アルマのなかではつかみどころがないのだった。
それでも、いつものように店番をしていてふと客足がとだえ、ひとりになったとき、アルマは時たま戸棚の奥にしまいこんだあの硝子びんのことを思い出す。一緒に残されていた小さな桜貝は、いまは硝子びんのなかでふたごの烏貝に寄り添っていて、アルマがびんを棚から取り出すたびに、かちんかちんと小さな音を立てるのだ。しっかりと殻をとざしている烏貝と、冷たい殻だけになってしまった桜貝は、それ以外はもうなにもしゃべらずに黙りこくったままだ。それでも、アルマがこっそり硝子びんを耳に当ててみると、びんを満たす水のどこからか、あるいはアルマの耳の奥のどこからか、若いきょうだいが網をひきながら交互に叫ぶ、やあいやあいという呼び声が聞こえてくる気がする。遠い異国できっと鳴り響いていた磯の唄が、そうして聞こえてくる気がする。