 OU FUCKIN' RAT! OU FUCKIN' RAT!5
冴えきった秋空がどこまでも広がるその下に、カリャンスクの丘はなだらかな稜線を描いて横たわる。時たま緑の曲線が不意に険しい崖になり、裸の土壁を遠目に見せているが、その崖の上には二、三匹の白い羊がぼんやりと草をはむ様子が見えて、おだやかに流れる風と時を感じさせるのだった。そのすぐ上にはもくもくと雲がわだかまっているが、雨はいまだはるかに遠い。 収穫も間近な田園のあちこちは黄金色に染まっており、そのなかにぽつりぽつりと見えるわらぶきの屋根に、正午も近い時刻の太陽が日光をさんさんと惜しみなく送っていた。 そんな中でもひときわ控えめな、こじんまりとした屋根の下で、いまデューラムは粗末な木のテーブルに腰掛けている。今日も外はあたたかかったが、小さな窓を一つ・二つ持つだけの彼の居間・兼・客間・兼・食堂はどことなくひんやりしている。黒ずんでところどころ剥がれ落ちたしっくいの内壁が印象をより暗めにしていた。さして何があるでもないそんな粗末な部屋のあちらこちらを、遠慮もなく覗いたりひっくり返したりする後ろ姿を、デューラムはぼんやりと眺めているのだった。 暖炉の横の大きなブリキのバケツの上に無造作にかけられていた粗布をひっぱりあげると、もうもうとほこりが立つ。その下を覗き込もうとした女は、大げさに顔の前で手を振るとデューラムを振り返った。これみよがしに咳をしながらデューラムを睨みつける。 「掃除なさいよ、もっと」 「してるさ」デューラムはテーブルに肘をついたままぶっきらぼうに答えた。 「こんなのしてるうちに入りゃしないわよ、むさくるしいのねえ」 なおも愚痴を垂れながら、エーリーンは擦り切れた麻布をがらくたの入ったバケツの上に放り投げた。それから彼女は黒煉瓦の暖炉を、壁の隅に空いたいくつかの小さな穴を、そうして壁にくくりつけられた小さな木棚をざっと点検すると、ふうんと声を出してデューラムを見やった。 「いや、本当の話なんだ」疑惑とも納得ともつかぬ彼女の声に不安をおぼえ、デューラムは弁明した。「昼間は静かなもんだから疑うのも分かるが」 「ううん、疑ってるわけじゃないわ」あごの尖った瓜実顔が天井をぐるりと見上げると、豊かな巻き毛がその背中でざらりと揺れる。「そうね、きっと何かいるんでしょうね。……報酬は?」 「報酬?」デューラムは呆れて口をぽかんと開けた。「友達から金を巻き上げる気か? おれがきみのとこの雨漏りを直したときには、見返りなんてはなから期待してなかったぞ……」 「あらだって、あれはあんたが見返りを要求しなかったんですもの! あたしはもっと現実主義なのよ」エーリーンは肩をすくめてから、にんまりと彼に笑いかけた。「ね、こんなのはどう? あんたの可愛い恋人に一回キスさせてよ!」 デューラムは頭を抱えた。今日はどうやら機嫌が良いようだったが、機嫌が良いは良いなりに面倒である。「おれの可愛い恋人なんてどこにいるんだ? こっちが聞きたいよ」 「あら、ダグラスが言ってたわ、最近つきあいが悪いのはかわいこちゃんの恋人ができたせいだって! 隠してないであたしにも見せなさいよ」 「おれがつきあいが悪いだなんてやつが言ったのか? そりゃこのごろは収穫の準備で少し忙しかったが――まあどうでもいいが」デューラムは溜息をつくとがりがりと頭を掻いた。「その可愛い恋人がたとえいたとしてもおまえには会わせないぜ。何をされるかわかったもんじゃない。下手したらもう帰ってこなくなりそうだ」 「まあ! あたしがまるで人さらいの妖怪みたいに言うじゃないこと?」 「妖精の血をひいているといったのはおまえだろ?」 言ってやると、エーリーンはきゃはっと声をあげて笑った。「そうだったわ。仕方ないわね――外、出るわよ」 答えも聞かずに、彼女は身を翻すとさっさと扉を出て行ってしまった。 彼女のあとを追っておもてに出ると、エーリーンは裏口にほど近い場所にしゃがみ込んでいた。 「何かいたか? ……おれもそこは覗いてみたが、暗くて何も見えやしないんだ」 エーリーンはちらりとデューラムを見たが、答えず、しゃがんだ姿勢のまま背中を丸め、地面すれすれまで首を伸ばした。家の台所は他の部屋より一段低くなっていて、裏口のすぐ横の壁の地面にほど近い場所には、他の部屋の土台部分につながる通気孔が開いている。鉄の柵で閉じられたその四角い通気孔のあいだから、その奥の闇を彼女は覗き込んでいるのだった。 デューラムは彼女のとなりにかがんだが、エーリーンが赤毛を地に垂らし壁にはりつくように土台を覗いているので、彼には割入るすきまがなかった。とりあえずぼんやり様子を眺めていると、ふいにエーリーンが顔をあげてデューラムの顔を覗き込んだ。 「ね、あんた鼠捕り持ってて? ちょっと中から持ってきてくれて?」 「いやあ、鼠じゃないぜ。鼠捕りならおれももう何度も試してるんだ。あのバチンといくやつでな……ふだんの鼠なら普通にやっつけられるが、今度のはいくらやっても駄目なんだ。鼠より大物で、もっと狡賢いやつだと思うんだが、おれは」 「やり方がまずいのよ」と、エーリーンはにべもない。「むさくるしいやり方じゃ、いやらしい鼠は捕まらないの。……いいから持ってきて。それにチーズ……そうね、ちょっとかびの生えた匂いの強いのがいいわ」 合点のいかないデューラムだったが、抗ってどうなるものでもないので、仕方なく彼女の指示に従うことにした。裏口から台所に入ると、戸棚の中からチーズを取り出し、よく熟してどろりと芳香をはなつひとかけらを切りとる。床の上に置きっぱなしになっていた大型の鼠捕りとともにチーズを窓越しにエーリーンに手渡し、少し考えてから、念のために鍵付きの木箱にしまってあった小剣を取り出す。そうして外に出たところで、デューラムはぎょっとして立ち止まったのである。 エーリーンは相変わらず裏口の横にしゃがみこんでいた。ほとんど地面にうつぶせになるようにして、片方の手を通気孔から深く差し入れ、さらにはその顔すらも鉄の柵に触れんばかりに近づけていた。デューラムを立ち止まらせたのは、ほかでもないその姿態である。床下を覗き込むように伸びた首の白い曲線が、なぜだか突然ひどく土臭く淫らなものに見えたのだ。もしかしたらそれは横顔の表情のせいかもしれない。彼女の唇はいまやかすかに笑んでいて、その緑の目はまつげを伏せるように細められている。さきほど家の中にいたときとはうってかわった、何者かに優しく話しかけるような、それでいてしなだれかかるような、奇妙な表情だった。幾筋かの髪の束が乱れて額から口元あたりに落ちている。顔には泥が少し跳ねており、白い頬にいわく言いがたい染みをつけていた。うっすらと開いた色の薄い唇はたしかに何事かを囁いており、時折ピンク色の舌がちらちらとのぞく。独り言か、まじないか、何を言っているのかは聞き取れなかったが、まるで何者かが悪意をこめて子供や若者を誘うときのような口調――それでいてひどく甘ったるい響きを含んでいるように思われた。 彼女にかけようとした声をデューラムは呑み込んだ。いま話しかけてはいけないという気がした。邪魔を避けようとする意志ではあったけれども、それに先だったのは、むしろ彼女自身に対する頭の中の警鐘だった。自分が唾を飲む音が驚くほど大きく口の中に響いた。 しかし、一瞬のちのことである。 ばしんと激しい音がした。ついで甲高い獣じみた叫び声が床下から一つ、空気を鋭く切り裂き鼓膜を打ったかと思うと、同時に、 「やったわ!」エーリーンが大声で叫んだ。 デューラムはぱちくりと目をしばたたかせる。 すると彼女はもういつものとおりの彼女で、土台の入り口の近くに土まみれで四つんばいになっているだけなのだった。 「捕まえたわ!」エーリーンはそう叫び、いつから気づいていたのか、泥が飛んでくしゃくしゃになった巻き毛の中から嬉しそうな笑顔をデューラムに向けた。 デューラムは呆気にとられてその姿をまじまじと眺め直したが、細い手足が少しがにまたに地面にうつぶせている、ただそれだけである。なぜ先ほど忌避感などを感じたのか今となってはさっぱりわからなかった。 デューラムは彼女に駆け寄った。「やっぱり鼠だったのか?」 「ええ」言って、エーリーンは小さく舌打ちした。右腕はまだ深く鉄柵の間に突っ込まれていて、その向こうで彼女が何を掴んでいるのかは見ることができない。 「もう、大人しくなさい! まだ生きててやたら暴れるの」 「鼠捕りに引っかかったまま踏ん張ってるのか? えらいしぶとい奴だな、おれが代わ……」 だが、そこまで言ったところで、デューラムは鉄柵の奥の闇から聞こえてきた耳ざわりな声に息を呑んだ。きいきいと甲高いその声は、獣じみてはいるものの到底鼠のもののようには思われなかったからである。聞きようによっては中年男のようにも思われるひどく濁った声で、しかもデューラムに理解できる言語ではなかったが、まるで誰かをおそろしい勢いで口汚く罵っているかのように響くではないか! そのトーンから察する限り、なにか、ひどく卑猥で中傷じみた罵りを…… 「おい、ちょっと待て、これ――」デューラムは視線を険しくすると小剣を鞘から引き抜いた。「――これ、鼠じゃないだろう。手――おまえ、そいつ捕まえてる手、大丈夫なのか!」 そう言うあいだにも罵り声はひどくなる一方である。ますます高く、ますますどぎつく、ますます早口になり、その意味も意図もわからないのに、胸くそ悪くなる汚らしい罵声だということだけには絶対の確信が持てるのだ。そのわめき声の合間にはどたんばたんと何者かが床下で激しく暴れる音がし、エーリーンの体が通気孔の奥に向かってずるりと引きずり寄せられた。彼女は左手をふんばって小さく呻いた。 「おい、早くその手をやつから放して引っこ抜け!」 デューラムは鋭く言うとエーリーンを押しのけようとした。「おれが代わるから――」 「大丈夫、ただの鼠よ!」 デューラムの声をさえぎって、歯を食いしばりながらエーリーンは叫んだ。 「ただの鼠! そうでしょ、このげす野郎(ファッキン・ラット)!」 次の瞬間、エーリーンは右腕を床下の暗闇の中から勢いよく引きずり出していた。 デューラムはその手の先にぶら下がるものを見て、自分の目が信じられずに唖然とした。鼠捕りの強力なばねと木板の間に挟まれて体をぶらぶらと揺らしているその生き物は、つい先ほどまでは確かに家の下の暗がりで、騒々しく暴れながらおぞましい罵声をエーリーンに吐いていたはずであるのに、白昼の日のもとにさらけ出されてみれば、まごうこともなく一匹のどぶ鼠(ラット)にほかならないのだった。ただし、おそろしく大きい。鼠捕りに胴体を囚われたまま空中につり上げられたその子犬ほどもある鼠は、いまや観念したように大人しく、後ろ足で怠惰に空中を掻いているばかりだった。 「見てこの大きいこと、よく育って、人間にしたら中年親父ってとこかしらね? まったくいやらしくて嫌になっちまうわ。でも、おびき出しやすくって助かったわ」 快活に笑うと、エーリーンはデューラムに向かって鼠を持つ腕を付きだした。 デューラムは困惑しながらも鼠取りを受け取り、立ち上がった。彼の手に渡った灰色の鼠は、みみずのような質感の長い尻尾を、まるで蛇か蜥蜴がとぐろを巻くようにゆっくりと巻き上げている。その顔を近くで覗き込んでデューラムはぎょっとした。鼠がなにやら黄色くじめじめと濁った、怨嗟のこもった目でデューラムを睨み返したからである。ただし目をまたたいてもう一度見ると、それはただの、何を見ているのかも知れない黒い動物の目にすぎないのだった。 デューラムは溜息をつくと、鼠をぶらさげたままエーリーンに目をやった。 「どうしたもんかな」 「あんたの自由だけど、殺したほうがいいかもよ――このへんに放したらまた家の下に入るわよ。この家のこと、そりゃ気に入っていたみたいだから」 エーリーンは髪にこびりついた泥を落とそうと苦心しながら、「しかもなんだかこの鼠、凶暴でいやらしい顔をしてるし、あんたの可愛い恋人がこの家で寝てるあいだに、その娘の脚だの胸だのを齧ったりするかもしれないことよ」 デューラムは呆れて天を仰いだ。「だからその可愛い恋人の話は忘れろよ!」 先ほどあれほど暴れて抵抗した鼠ではあったが、地面にうつぶせに横たえ、うなじに小剣の横刃を当てて尻尾をくいと強く引くと、あっけなくも息絶えた。 「悪いがおれも死活問題なんでな」 デューラムは呟くと、近くの木の下に小さな穴を掘り、鼠の死体を埋めてやった。秋風にざわざわと葉をそよがせるその木は、デューラムの家の周囲でも一番の大木である。土中に伸びた無数の根はすぐにもその小さな死体を包み込み、さらに青々とした葉を茂らせるだろう。 「あら、これ桜じゃない! あんたも気が利かないようでいて洒落たことするのね。ちょっと見直したわよ」 「はあ?」 背後のエーリーンの声に、振り向きざまデューラムは間抜けな声で答えた。だがなんのことかを問いただす前に、彼女はにんまり笑うと彼の目の前に茸を一本ぶら下げた。いつ家の中から取ってきたのやら、“妖精の輪”に生えていたくだんの茸である。 「ね、デューラム、あたし思い出したの。これ、蒸したり炙ったりすると美味しい茸だわ。それにたしか、食べると元気がつくって言われてるはずよ。だって、この形、ねえ……」 そこで彼女はさも意味ありげにくすくす笑うと、「うふふ、みんなにわけるのもったいないわ。土瓶蒸しにしてさっさと二人で食べちゃわないこと?」 含み笑いを浮かべたエーリーンの顔を、デューラムは訝しんで見返した。「土瓶なんぞうちにあったかなあ……。しかしおまえ、それ毒茸だって言ってただろう」 エーリーンは首をのけぞらせるようにして、きゃはっといかにも嬉しそうな笑い声を上げた。「きっと、あんまり多く食べると元気になりすぎて毒になるんだわ。とくに男の子がファタの一人と一緒に食べてるときなんかは! 気をつけてちょうだいね、デューラム!」 それから彼女はぽかんと口を開けたままのデューラムの顔を覗き込み、にんまりと目を歪めて囁くのだ。 「うふふ、冗談よ、大丈夫。そんなに量がないし……だいいちあたしはファタとしてはまだまだ修行中の小娘なんですもの。心配しないで」 言うなり、またもやいかにも楽しそうにエーリーンは笑いつづけるのだった。妙に含みのある発言だとも思いつつも、それのどこからどこまでが冗談なのか、冗談だとしても何が面白いのかデューラムにとってはさっぱり理解不能だった。ただ、ふと、ころりとして太く大きなその茸に唇を寄せてエーリーンがこちらに視線を流す、その光景があまりじろじろ見るべきものではない気がして、彼は目をそらした。どこからそんな思いがわいてきたのかも、なぜ自分の顔が気まずさか羞恥のために火照るのかも、彼にはやはりわからなかった。いずれにせよ、エーリーンがその血をひいていると自称する生き物の名、ファタを、彼は三度目にしてようやくぼんやりと記憶にとどめるのである。 のちになって、デューラムはその日二人で食べた茸(たしかに香り高い、非常なる珍味であった)がtricholoma matsutakeとかいう長たらしい名前の茸と知ることになる。クリッサがそれこそ彼女のほしがっていた媚薬の原料だと言って、その奇妙な響きの名を連呼しながら、文字通り地団駄をふんで悔しがったのだった。話題を変えてその怒りをやりすごすために彼はツァランに尋ねた。「なあ、ファーターだか、ファダか……そんな単語、聞いたことあるか?」 「知らないなあ」ツァランは当惑したように眉を寄せ、しばらく考えてから顎を撫でた。「いや、fata(ファタ)といったか? もしかしてあれかな、西国の言葉で妖精……だったかな。古典語では“語られしもの”とかいう意味で、フェアリーだのフェイだのの語源だな。<運命の女(ファム・ファタール)>のファタールもそれだぜ。つまり…… ……時として、毒婦、妖婦のことだ。……それがどうかしたのか?」 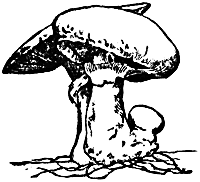 Toadstools
もしよければ……
|